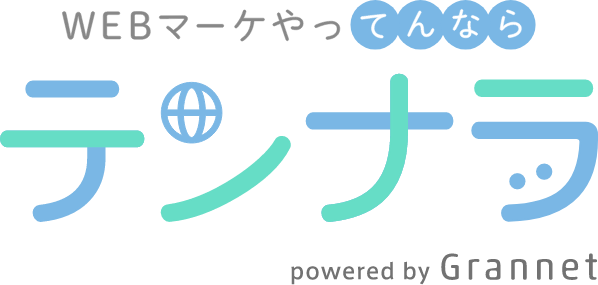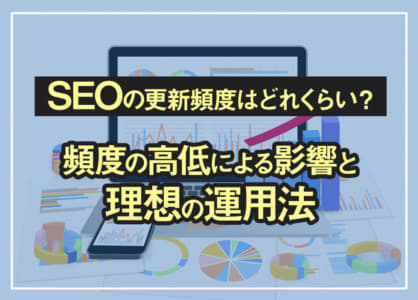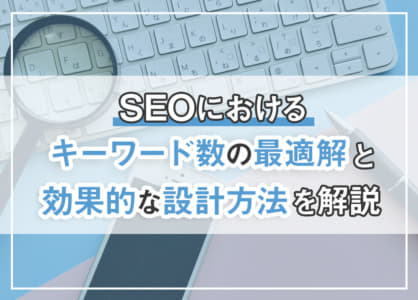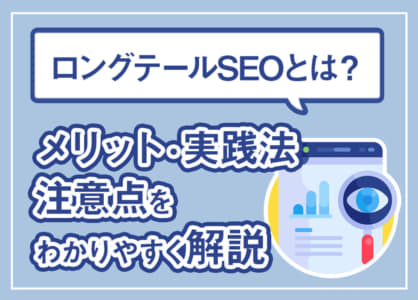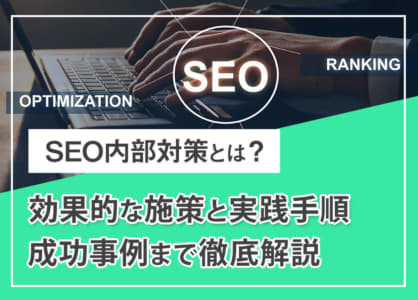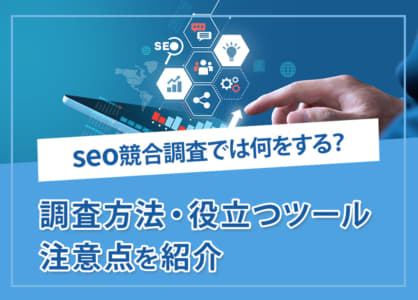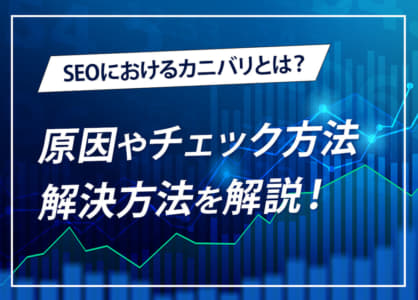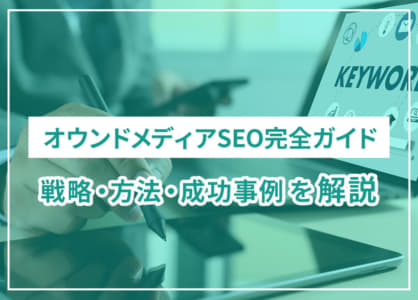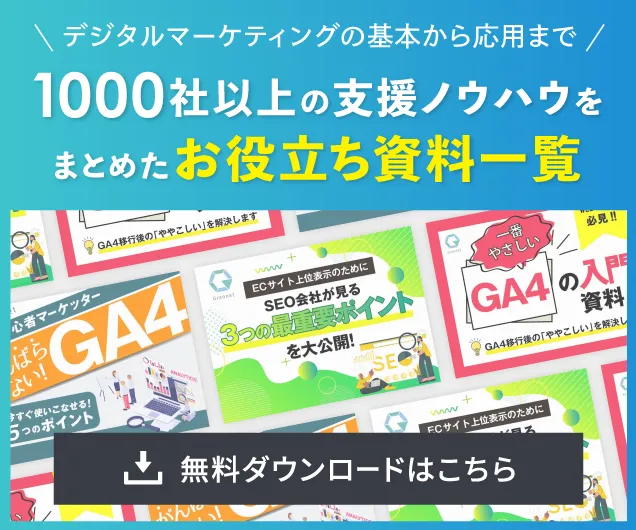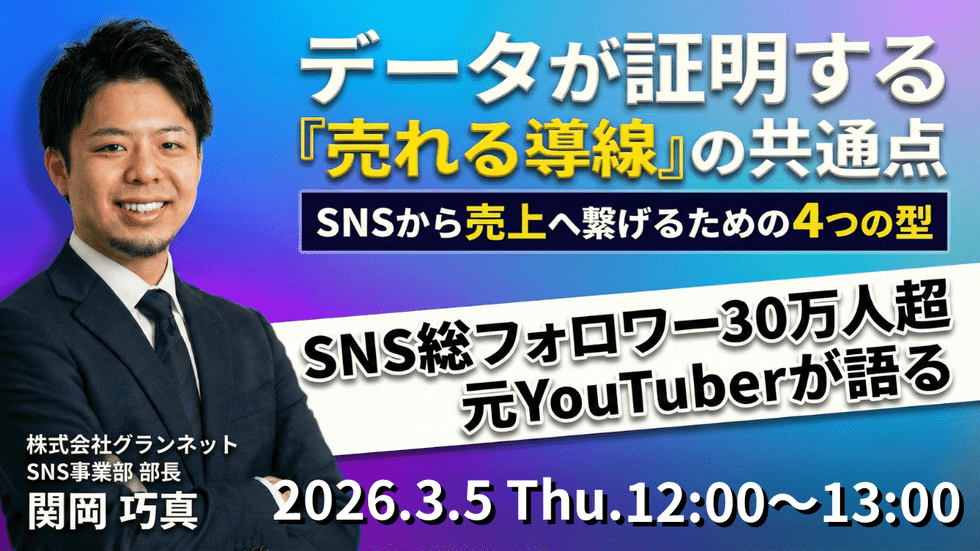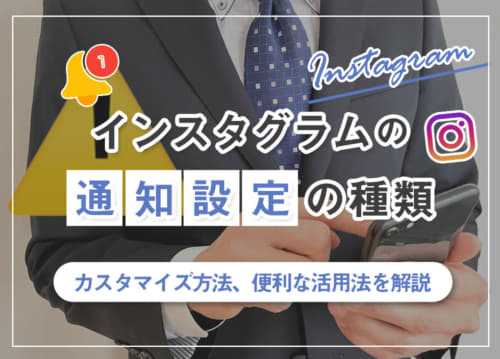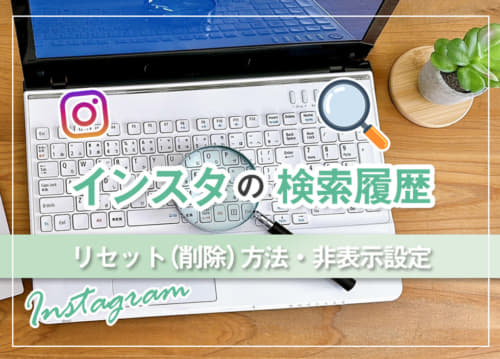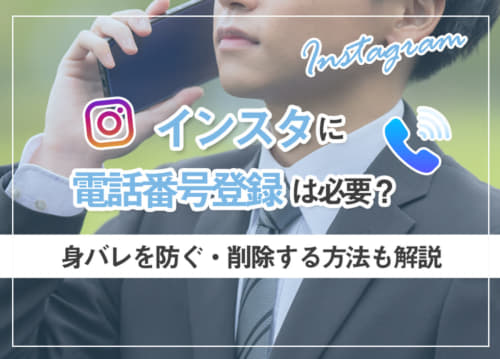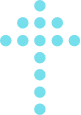採用サイトにおけるSEOのメリットや効果的な施策・事例を紹介
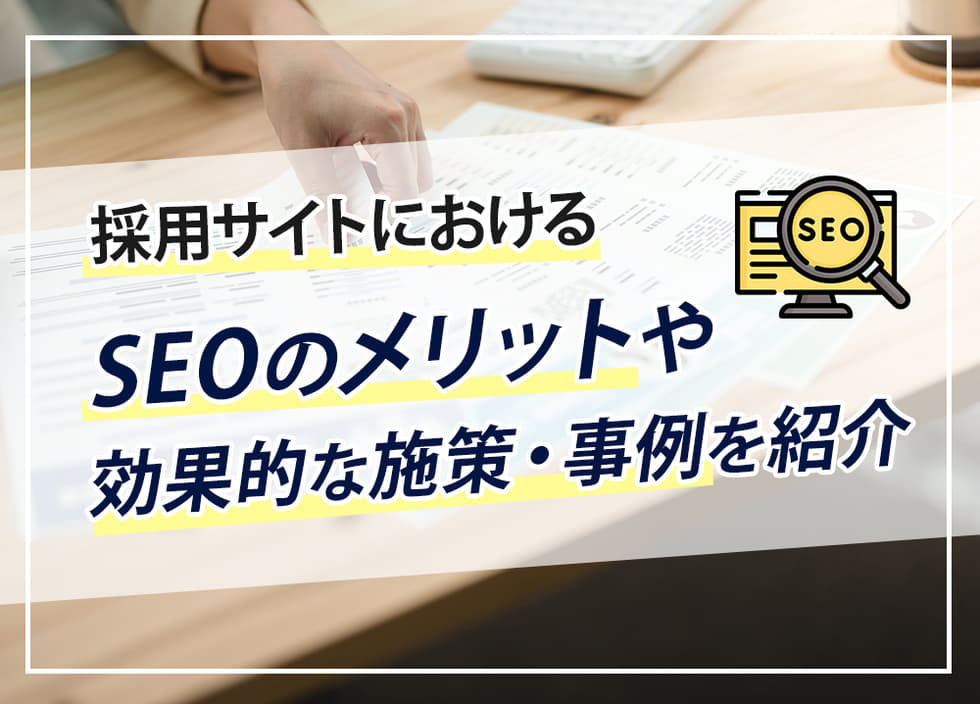
企業の採用活動は求人媒体や人材紹介に依存する傾向がありますが、近年は自社の採用サイトを軸にした集客が注目されています。その中でも、検索結果で上位表示を目指す「採用サイトSEO」は、継続的に応募者を獲得できる有効な手段です。SEOを正しく理解し実践することで、採用コストを抑えつつ、自社にマッチした人材と出会える可能性が高まります。
当記事では、採用サイトSEOの基本からメリット・注意点、具体的な施策や成功事例までを徹底的に解説します。
1. 採用サイトにおけるSEOの重要性
採用サイトは、企業が求職者に向けて情報を発信する重要な窓口です。近年では、就職・転職活動を行う多くの人がインターネット検索を活用して企業情報を調べ、応募先を比較検討するようになっています。
もし検索結果に自社の採用サイトが表示されなければ、せっかくの求人情報も閲覧されず、応募機会を逃す恐れがあります。そのため、採用活動を効率的かつ継続的に行ううえで「採用サイトSEO」は欠かせない施策といえます。
SEO対策によって検索エンジンでの可視性を高めることで、自社をまだ知らない潜在的な候補者にリーチでき、応募者数や質の向上につながります。
1-1. 採用サイトとコーポレートサイトの違い
採用サイトとコーポレートサイトは混同されがちですが、目的と設計思想が大きく異なります。コーポレートサイトは企業全体の事業内容や実績、サービス紹介を中心に構成され、主に顧客や取引先に向けて信頼性を伝える役割を担います。
一方で採用サイトは、求職者が知りたい情報を的確に提供し、応募につなげることが目的です。たとえば「募集要項」「福利厚生」「社員インタビュー」「キャリアパス」などは採用サイトならではのコンテンツです。SEOを実施する際も、コーポレートサイトで狙うキーワードとは異なり、「新卒採用」「エンジニア 採用」「地域名+求人」など、求職者目線で検索されやすいキーワード設計が必須です。
両者を明確に分けて戦略を立てることが、成果を高める第一歩です。
1-2. 求職者の情報収集行動と検索エンジンの関係性
求職者は、求人媒体で気になる企業を見つけても、すぐに応募するとは限りません。多くの場合、Google検索で企業名や職種名を調べ、自社の採用ページや口コミサイトを確認してから応募を検討します。特に若年層は、企業公式サイトから「社員の雰囲気」「キャリア支援」「働きやすさ」といった情報を探す傾向が強いです。ここで検索上位に表示されていなければ、候補者は競合他社の情報に流れてしまいます。
SEOで上位表示されることは、アクセス数を増やすだけでなく、「信頼できる企業」という印象を与える効果もあります。検索結果に出てこない企業は、それだけで候補から外れてしまう可能性があるため、SEOは応募率や採用ブランドの形成に直結するといえるでしょう。
2. 採用サイトSEOの基本的な考え方
採用サイトにおけるSEOは、一般的なWebマーケティングにおけるSEOと同じ基本原理に基づいています。ただし、目的は商品やサービスの購入ではなく「応募」という行動に直結する点が大きな違いです。求職者が検索するキーワードは業界や職種、勤務地などが中心であり、検索結果で上位に表示されれば応募検討の入口となります。
SEOの考え方を正しく理解しておくことは、長期的に安定した応募者獲得の基盤を築くうえで重要です。ここでは、採用サイトSEOにおける基礎的な視点と、求人媒体との違いについて整理します。
2-1. SEOの基礎用語と採用サイトでの応用
SEOを理解するには、基本用語の把握が欠かせません。代表的なものとして「キーワード」「検索意図」「内部対策」「外部対策」「コンテンツ最適化」などがあります。採用サイトにおいては、これらを求職者目線に置き換えて考えることが重要です。
- キーワード:職種名(例:営業職、エンジニア)、勤務地(例:東京、福岡)、雇用形態(例:新卒、中途、アルバイト)など。
- 検索意図:求職者は「この会社で働けるのか」「待遇はどうか」を知りたい。その意図を満たす情報を提供する必要がある。
- 内部対策:サイトの構造を整理し、募集要項や社員紹介ページを検索エンジンが正しく認識できるようにする。
- 外部対策:求人ポータルやメディアからリンクを獲得し、採用サイトの信頼性を高める。
単なるキーワードの羅列ではなく、「検索者=求職者が知りたいこと」を中心に据えることが、採用サイトSEO成功のポイントです。
2-2. 求人媒体との違い|SEOで狙える成果とは
求人媒体は、短期間で多くの求職者にリーチできる利点がありますが、掲載終了と同時に効果は途切れてしまいます。一方、採用サイトにおけるSEOは成果が出るまでに時間を要しますが、上位表示を獲得できれば継続的に応募者を集められる資産的な仕組みになります。
さらに、求人媒体ではフォーマットが決まっており差別化が難しいのに対し、自社採用サイトでは自由に情報を発信できます。たとえば、社員インタビューや働き方の紹介、動画コンテンツを盛り込むことで、自社ならではの魅力を伝えられます。
SEOで成果を狙う場合は、単なる「応募数の増加」だけでなく、求職者の理解度やマッチ度を高める効果も期待できます。つまり、採用の質と効率を両立できるのが、採用サイトSEOの大きな特徴といえるでしょう。
3. 採用サイトSEOのメリット
採用サイトにSEOを導入する最大のメリットは、中長期的に応募者を獲得し続けられる点にあります。求人広告のように掲載期間が限られる施策と異なり、一度上位表示を達成すれば、継続的に検索流入が見込めます。また、広告費用をかけずに求職者の目に触れる機会を増やせるため、採用コストの最適化にもつながります。
さらに、採用サイトが求職者にとって役立つ情報源として認知されれば、自社の採用ブランドを高め、競合との差別化も可能です。
ここでは、具体的な3つのメリットを解説します。
3-1. 中長期的に応募者を獲得できる仕組み
SEOは成果が出るまでに一定の時間を要しますが、一度検索上位を確立できれば安定した応募者獲得の仕組みになります。たとえば「東京 営業職 採用」などで自社の採用サイトが上位表示されれば、広告を出さなくても自然に応募者が流入してきます。
- 広告掲載終了後も応募が続く
- 露出が安定するため採用計画が立てやすい
- 特定の職種や勤務地に強みを持つ企業は継続的に効果を発揮できる
このように、短期的な集客に依存せず「資産」として応募チャネルを築けるのが大きな強みです。
3-2. 採用コストの削減と費用対効果の向上
求人媒体や人材紹介サービスを利用すると、1名の採用に数十万円〜100万円以上のコストがかかることも珍しくありません。その点、採用サイトSEOは初期の制作費用や運用工数は必要ですが、長期的に見れば費用対効果が非常に高くなります。
- 求人広告費を抑えられる
- 成功報酬型の人材紹介に依存しない採用が可能
- 継続的に成果を得られるため、1人あたりの採用単価が低下する
採用人数が多い企業や継続的に採用を行う企業では、広告に依存するよりもSEOに投資する方が、結果として大幅なコスト削減につながります。
3-3. 自社の採用ブランド力を高められる
採用サイトでのSEOは、単なる応募者獲得だけでなく、企業の採用ブランドを構築する効果もあります。検索結果の上位に表示されること自体が「信頼されている会社」という印象を与え、応募意欲を後押しします。また、社員インタビューや福利厚生紹介、社内イベント記事などを通して「この会社で働きたい」と感じさせることも可能です。
- 認知度が低い企業でも検索を通じて候補者に発見されやすい
- コンテンツを通じて会社の理念や働き方を伝えられる
- 競合との差別化によって、自社にマッチした人材を惹きつけられる
長期的には、SEOを軸にした情報発信が企業文化や価値観を外部に浸透させる「ブランディング施策」としても機能します。
4. 採用サイトSEOのデメリット・注意点
採用サイトSEOはメリットが大きい一方で、すべての企業にとって即効性のある万能施策ではありません。成果が出るまでには時間がかかり、運用には専門的な知識や継続的な改善が必要です。また、競合との争いが激しい領域では差別化が難しく、狙ったキーワードで必ずしも上位表示できるとは限りません。
こうした注意点を理解したうえで戦略を立てなければ、期待した効果を得られない可能性があります。ここでは代表的な3つのデメリット・注意点を解説します。
4-1. 成果が出るまでに時間がかかる点
SEOは検索エンジンに評価されるまで一定の時間が必要です。採用サイトのように更新頻度が少ない場合、上位表示されるまでに半年以上かかるケースもあります。
- 新規ドメインでは評価が蓄積するまで時間がかかる
- 競合が多い職種や地域では順位上昇がさらに遅れる
- 即効性を求める場合は広告や媒体との併用が必要
短期間で応募数を増やしたい場合、SEO単独では限界があるため、長期的な投資と並行してほかの施策を組み合わせることが求められます。
4-2. 専門知識や継続的な運用が必要
SEOは一度設定して終わりではなく、アルゴリズムやユーザー行動の変化に合わせて改善を続ける必要があります。採用サイトでは「職種名」「勤務地」などのキーワードが頻繁に変化するため、放置すると順位が下がるリスクがあります。
- 定期的なキーワード見直しが必要
- コンテンツ更新(インタビュー記事や募集要項の追加)を続ける必要
- アクセス解析や順位チェックによる効果測定が必須
社内に知見がない場合は外部のSEO会社や採用コンサルティングを活用するのも選択肢となります。
4-3. 競合との差別化が難しいケース
採用市場は競争が激しく、同じような職種・勤務地で多くの企業がSEOを行っています。そのため、「エンジニア 採用 東京」といった一般的なキーワードでは競合大手に埋もれてしまう可能性があります。
- 汎用的なキーワードは大企業や求人媒体に上位を取られやすい
- 差別化要素が乏しいとクリックされても応募に至らない
- 自社独自の魅力や情報発信が求められる
ニッチな職種や地域に絞る、独自の社風や働き方を具体的に発信するなどの工夫が必要です。SEOテクニックではなく、採用戦略全体の中での位置づけを意識することが成功につながります。
5. 採用サイトSEOの具体的な施策
採用サイトでSEOを実施する際は、基本的な考え方だけではなく、具体的な施策に落とし込むことが重要です。SEOの効果は複合的な要素で決まるため、キーワード選定からコンテンツ設計、内部施策や外部施策までを体系的に行う必要があります。また、近年はGoogle for Jobsなどの検索機能も普及しており、構造化データへの対応も見逃せません。
ここでは、採用サイトSEOにおける代表的な5つの施策を解説します。
5-1. キーワード選定の方法と注意点
採用サイトのSEO成功は、適切なキーワード選定から始まります。求職者が検索する言葉を想定し、競合状況や検索ボリュームを分析して選びましょう。
- 一般的なキーワード:「営業職 採用」「エンジニア 求人」など競合が多い。
- ロングテールキーワード:「新宿 営業職 中途採用」「未経験 ITサポート 求人」など、応募確度が高い。
- ブランド系キーワード:「○○会社 採用」「○○株式会社 インターン」など、自社名での検索対策。
注意点として、競合が強いビッグキーワードだけに依存せず、ロングテールを組み合わせることが重要です。また、求職者の検索意図に沿ったコンテンツを提供できるかを必ず確認しましょう。
5-2. コンテンツ設計|募集要項・社員インタビューの活用
SEOで上位を目指すには、求職者の疑問や不安を解消するコンテンツが欠かせません。募集要項はもちろん、実際に働く社員の声やキャリア事例を掲載すると効果的です。
- 募集要項:職種・勤務地・給与・福利厚生を明確に記載し、検索キーワードを自然に盛り込む。
- 社員インタビュー:働く環境や雰囲気を伝えることで、応募意欲を高める。
- FAQページ:「残業は多い?」「キャリアアップの流れは?」など、求職者の疑問を解決するコンテンツを設置。
これらのページを充実させることで、SEO評価が高まるだけでなく、応募前の不安解消につながり、質の高い応募者を集めやすくなります。
5-3. 内部対策|サイト構造・表示速度・モバイル対応
検索エンジンがサイトを正しく理解できるようにする「内部対策」も重要です。特に採用サイトは求職者がスマートフォンで閲覧するケースが多いため、モバイル対応は必須です。
- サイト構造:職種・勤務地別にカテゴリを分け、URLやパンくずリストを整理する。
- 表示速度:画像サイズの圧縮やキャッシュ設定を行い、離脱率を低下させる。
- モバイル対応:レスポンシブデザインを採用し、スマホでもストレスなく閲覧できるようにする。
内部対策が不十分だと、コンテンツがどれだけ充実していても評価されにくくなるため、基盤整備を怠らないことが重要です。
5-4. 外部対策|被リンク・採用広報との連動
外部からの評価を高める「被リンク」もSEOの順位に影響します。採用サイトの場合、自然な形でリンクを獲得することが求められます。
- 採用広報記事:プレスリリースやオウンドメディアに掲載し、自社採用ページへリンクを設置。
- 大学・専門学校との連携:キャリア支援ページなどからリンクを獲得できるケースもある。
- SNS活用:TwitterやLinkedInで採用情報を発信し、拡散を通じてアクセスとリンクを誘発。
不自然なリンク購入はペナルティのリスクがあるため、広報活動やパートナーシップを活用した自然な被リンク獲得を意識しましょう。
5-5. 構造化データ・スキーマを用いた求人情報の最適化
Googleは求人情報を検索結果にリッチリザルトとして表示する仕組み(Google for Jobs)を提供しています。これに対応するには、求人情報に構造化データを設定することが有効です。
- JobPostingスキーマを利用して「職種名」「勤務地」「雇用形態」「給与」などをマークアップする。
- 正しく設定すれば、検索結果に求人情報が直接表示され、クリック率が向上する。
- Indeedや求人アグリゲーターとも連携しやすくなる。
採用サイトのSEOでは、順位を上げるだけでなく、検索画面上での視認性を高める工夫が成果につながります。
6. 成功する採用サイトSEOの事例
採用サイトSEOは理論や施策を理解するだけではなく、実際の事例を参考にすることで効果的なイメージをつかみやすくなります。中でも、検索流入から応募増加へとつなげた企業や、地方や中小企業がSEOで成果を出したケースは、多くの企業にとって参考になるポイントが多いです。
ここでは代表的な事例を2つ紹介します。
6-1. 検索流入から応募数増加につながった事例
あるIT企業では、新卒採用ページをSEO対策した結果、検索流入が前年比で約2倍に増加しました。取り組みのポイントは以下の通りです。
- キーワードの明確化:「エンジニア 新卒採用」「インターン 東京」などターゲット層に合わせた複合キーワードを設定。
- コンテンツ拡充:募集要項だけでなく、社員インタビューや1日の業務スケジュール、福利厚生紹介を追加。
- モバイル最適化:アクセスの7割がスマートフォンであったため、表示速度改善とUI改修を実施。
結果として、検索流入が安定し、応募数が大幅に増加しました。さらに、事前に社風や仕事内容を理解した応募者が増えたことで、採用のミスマッチ削減にもつながりました。
6-2. 地方・中小企業がSEOで成果を上げた事例
地方の製造業企業では、人材確保が課題となっていましたが、SEOを活用することで応募者獲得に成功しました。具体的には以下のような取り組みです。
- 地域名を含むキーワード戦略:「長野 製造業 求人」「地方 工場 採用」などニッチな検索ワードを重視。
- 独自の強みを発信:地域に根ざした働き方や、社員定着率の高さをコンテンツで訴求。
- 求人媒体と併用:媒体で認知を獲得しつつ、興味を持った求職者が自社サイトを訪れた際にSEOで上位表示される導線を整備。
上記の取り組みを行った結果、これまで応募がほとんどなかった自社サイト経由での応募が増え、広告費の削減にも成功しました。大手と比べて認知度が低い企業こそ、SEOを活用する価値が大きいことがわかります。
7. 採用サイトSEOの運用・改善のポイント
採用サイトSEOは、一度対策を行えば終わりというものではありません。検索エンジンの評価は常に変化し、求職者の検索行動やトレンドも移り変わります。そのため、継続的にデータを収集・分析し、改善を重ねていく運用体制が大切です。ここでは、アクセス解析や応募データの活用、改善サイクルの回し方、トレンドへの対応について解説します。
7-1. アクセス解析・応募データの計測方法
SEOの効果を測定するには、アクセス数や検索順位だけでなく「応募」という最終成果に至るデータを追うことが重要です。
- Google Analytics:流入経路やページ滞在時間、離脱率を確認し、改善ポイントを把握。
- Search Console:検索キーワードやクリック率、表示回数を分析し、狙ったキーワードで成果が出ているかを確認。
- 応募管理システム(ATS):応募者の流入元を計測し、SEO経由の応募割合を可視化。
上記を組み合わせて「どのページが応募につながりやすいか」「どのキーワードからの流入が成果に直結しているか」を把握することが、改善の第一歩です。
7-2. 改善サイクルの回し方(PDCAの実践)
SEOの成果は短期的には見えにくいため、計画的にPDCAサイクルを回すことが重要です。
- Plan(計画):ターゲットキーワードや改善施策を設定。
- Do(実行):コンテンツ追加、内部リンク調整、モバイル最適化などを実施。
- Check(検証):アクセス解析や応募数を確認し、成果を数値で評価。
- Action(改善):順位が伸びないキーワードや応募につながらないページを再設計。
PDCAサイクルを継続的に行うことで、採用サイトは徐々に強化され、安定した応募獲得が可能になります。
7-3. 求人トレンドやGoogleアルゴリズム変化への対応
採用市場は常に変化しており、求職者が検索するキーワードや関心も移り変わります。さらに、Googleのアルゴリズム更新によって順位変動が起こることも珍しくありません。
- 求人トレンドの把握:人気職種や働き方の変化(例:リモートワーク、DX人材)に合わせてコンテンツを更新。
- アルゴリズム対応:最新のSEO情報をキャッチアップし、品質重視のコンテンツを継続的に提供。
- 競合調査:同業他社の採用サイトを分析し、取り入れられる工夫を自社に反映。
柔軟に改善を重ねることで、外部環境の変化にも強い採用サイトを維持できます。
8. 採用サイトSEOにおけるよくある失敗と対策
採用サイトSEOは正しく運用すれば効果を発揮しますが、誤った進め方をすると成果が出ないどころか、かえって応募機会を逃すこともあります。ここでは、特に起こりやすい3つの失敗パターンと、その対策について解説します。
8-1. 求人票をコピーして掲載してしまうケース
求人媒体に掲載した募集要項をそのまま採用サイトに転載すると、検索エンジンから「重複コンテンツ」と判断され、評価が下がるリスクがあります。結果的に検索順位が伸びず、SEO効果を得られません。
この失敗を防ぐには、自社オリジナルの文章で求人情報を作成することが欠かせません。仕事内容や待遇条件はもちろん、社員のリアルな声や社風紹介など、媒体では伝えきれない情報を盛り込むことで独自性を高められます。求職者にとって有益な情報を意識的に追加することが最も効果的な対策です。
8-2. SEOを意識しすぎてユーザー視点を欠いたコンテンツ
「営業 採用 東京」などのキーワードを不自然に詰め込んだり、検索順位だけを意識して作られたコンテンツは、読みにくく応募意欲を削ぐ原因になります。SEOのために書かれた文章は、求職者にとっては単なるノイズになりかねません。
対策としては、まず「読みやすさ」と「分かりやすさ」を優先することです。応募を検討している人が知りたい情報は、具体的な仕事内容やキャリアパス、職場環境に関するものです。社員インタビューやQ&Aを交えると、自然にキーワードを含みながらも読みやすいコンテンツを作成できます。
8-3. 外部委託時に起こりがちなトラブルと対策
採用サイトSEOを外部に委託する場合、知識不足や認識のズレからトラブルになることがあります。たとえば、不自然な被リンク購入を行われてペナルティを受けたり、成果指標が「検索順位」だけに偏り、肝心の応募数につながらないケースです。また、すべてを外注任せにするとノウハウが社内に残らず、担当者が変わった途端に運用が止まる危険もあります。
こうしたリスクを避けるには、契約前に業者の実績や手法を確認し、ブラックハットSEOを行わないことを明示させることが重要です。さらに、成果指標は順位ではなく「応募数」や「応募の質」に設定することを忘れてはいけません。外注と社内担当者が協力し、定期的に効果検証を行う体制を整えることが、トラブル回避の最善策になります。
9. 採用サイトSEOと他施策の組み合わせ
採用サイトSEOは非常に効果的な施策ですが、単独で最大の成果を出すのは難しいケースもあります。理由は、SEOが成果を出すまでに時間がかかること、そして求職者の情報収集チャネルが多様化していることにあります。そのため、求人広告やSNS、動画活用など他施策との組み合わせによって、相乗効果を生み出すことが重要です。
ここでは代表的な3つの組み合わせ方を解説します。
9-1. 求人広告・求人媒体との併用方法
求人広告は即効性が高く、短期間で応募者を集められるのが強みです。一方でSEOは成果が出るまでに数か月かかるため、両者を組み合わせることで安定した採用活動を実現できます。
たとえば、新規募集を開始した直後は広告を使って集客し、その間にSEOを育てることで、中長期的には自社サイトからの応募を増やせます。結果として「短期の広告」「長期のSEO」という二本柱を構築できます。
9-2. SNS・オウンドメディアとの連動による相乗効果
近年、求職者は企業の公式SNSや社員の発信から情報を得ることも増えています。SNSで発信した記事を採用サイトに誘導することで、SEOの効果を高めることが可能です。社員インタビューやイベント記事は拡散性が高く、SEOでの検索流入だけでは届かない層に情報を届けられます。
さらに、オウンドメディアと連動させることで、企業文化や取り組みを継続的に発信でき、採用ブランド強化にもつながります。
9-3. 動画やIndeed・Google for Jobsとの活用法
求人情報をテキストだけでなく動画で発信する企業も増えています。職場の雰囲気や社員の声を動画で紹介することで、求職者が企業をイメージしやすくなり、応募意欲を高められます。また、IndeedやGoogle for Jobsと連携すれば、検索結果に直接求人情報が表示され、クリック率や認知度が向上します。
これらの施策はSEOと競合するのではなく、相互補完の関係にあるため、組み合わせることで応募導線が一層強化されます。
10. 採用サイトSEOを成功させるための体制づくり
採用サイトSEOは継続的な取り組みが必要なため、社内外を含めた運用体制をどう設計するかが成功の基となります。
SEO施策はコンテンツ制作、技術的な内部対策、効果測定の3要素が揃って初めて機能するため、どこまでを社内で担い、どこを外注に任せるのかを明確にしておくことが欠かせません。また、SEOは一度設定して終わりではなく、定期的な更新や改善を続けることが前提となるため、持続可能なフローを整備することが重要です。
最後に、自社運用か外注かの判断基準と、社内での担当者育成について解説します。
10-1. 自社運用か外注かの判断基準
SEOをすべて自社で運用する場合、ノウハウが蓄積しやすく、迅速な改善も行いやすいのが利点です。しかし、専任担当を置けない企業では、日常業務と並行して高度なSEOを実施するのは難しく、成果が出るまでに時間がかかることも少なくありません。逆に、外注すれば専門的な知識や経験を活かせる一方で、コストが発生し、情報共有が不十分だと効果が限定的になる恐れがあります。
この判断は「自社にSEOを学び実行できる人材がいるか」「中長期的に運用リソースを確保できるか」「外注コストを投資と捉えられるか」といった条件を基準に行うのが現実的です。短期的には外注で立ち上げ、並行して社内担当者を育成する方法も有効です。
10-2. 社内での担当者育成と運用フロー設計
採用サイトSEOを長期的に成功させるには、社内で一定の知識を持った担当者を育てることが重要です。SEOの専門家でなくとも、キーワード選定やアクセス解析の基本を理解し、外注先と対等に議論できるレベルであれば十分に機能します。
さらに、運用フローを明確にしておくことも重要です。新しい募集が始まったときにどのタイミングでページを公開するか、コンテンツ更新をどの部署が担うか、アクセス解析のレポートを誰が確認するかをルール化しておくと、属人化を防ぎ継続的な運用が可能になります。
SEOは小さな改善の積み重ねが成果に寄与するため、担当者が継続して関与できる体制を作ることが、長期的な成果を保証する最良の方法です。
まとめ
採用サイトSEOは、求職者の検索行動に応じて自社の情報を届けられる強力な手法です。
成果が出るまでに時間や労力は必要ですが、中長期的に応募数増加や採用コスト削減を実現できます。さらに、自社の採用ブランドを確立し、他社との差別化にもつながります。求人媒体やSNSなどの施策と組み合わせることで、より高い効果を発揮できるでしょう。
自社運用か外注かを含め、体制づくりを整えながら継続的に改善することが、成功のポイントです。