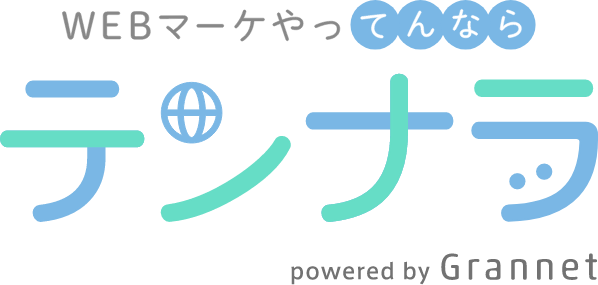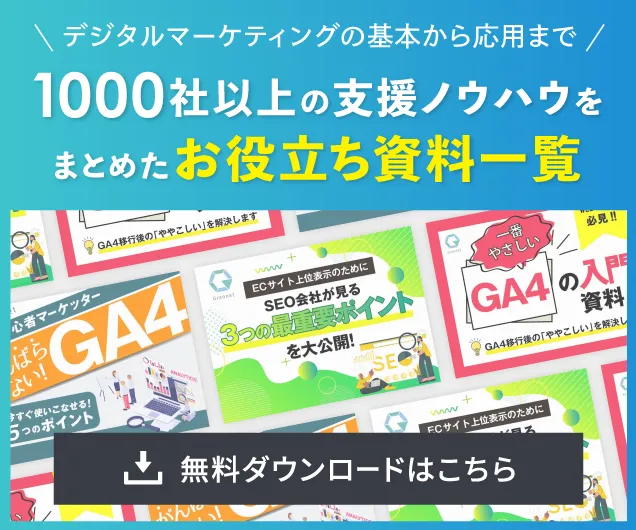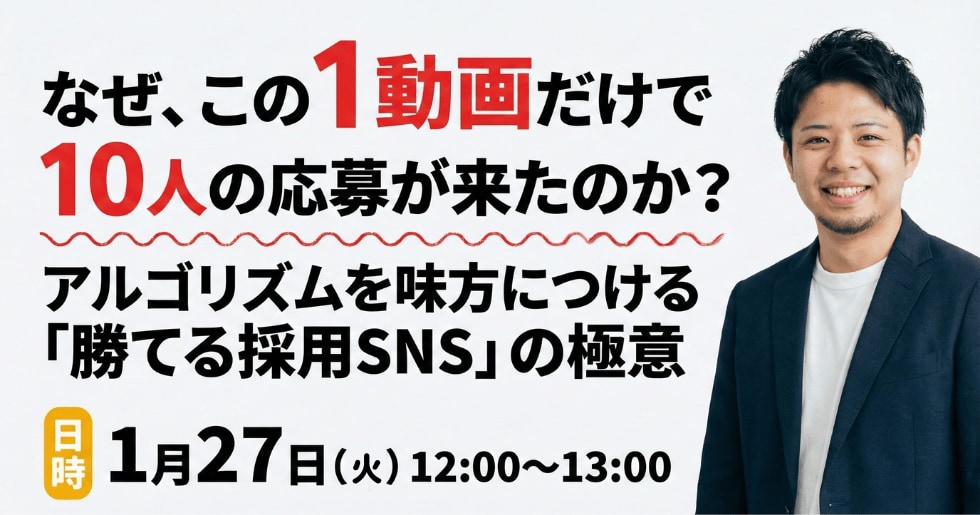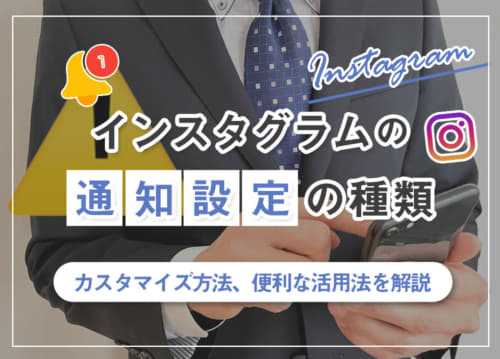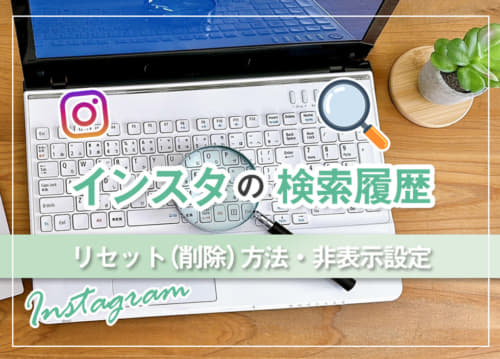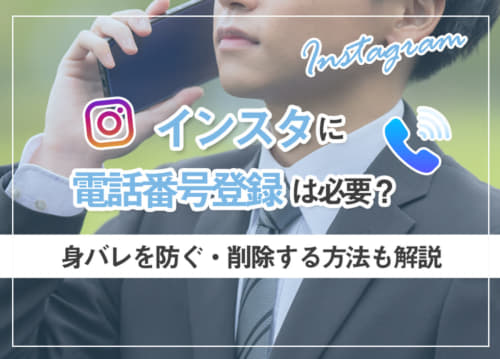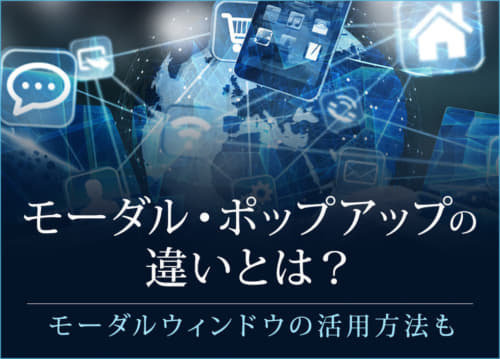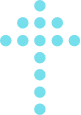オウンドメディアSEO完全ガイド|戦略・方法・成功事例を解説
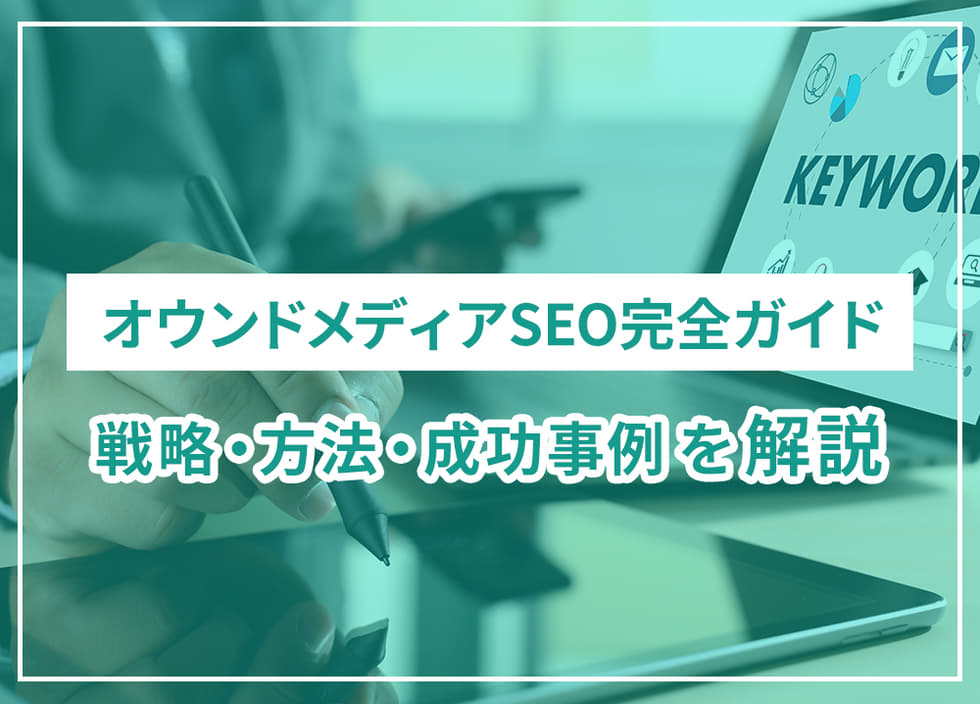
オウンドメディアSEOは、企業が自社で発信するメディアを活用し、検索エンジン経由で見込み顧客と接点を作る中長期的なマーケティング施策です。広告に頼らず、検索意図に応えるコンテンツを蓄積することで、安定した集客やブランド認知の向上が期待できます。とはいえ、やみくもに記事を増やすだけでは成果にはつながりません。ターゲット設計、キーワード戦略、構造設計、運用改善まで一貫した取り組みが必要です。
当記事では、オウンドメディアSEOの基本から実践方法、失敗事例、成功事例、KPIの設計までを具体的に解説します。メディア運用に携わる方はぜひ参考にしてください。
1. オウンドメディアSEOとは?
オウンドメディアSEOとは、自社が所有するWebメディア(ブログやコラムなど)を通じて、検索エンジンからの流入を獲得し、集客・ブランディング・CV(コンバージョン)につなげるマーケティング手法です。
広告のように出稿すれば即アクセスが得られるわけではありませんが、検索意図にマッチするコンテンツを蓄積することで、安定した自然流入と中長期的な成果を得ることができるのが大きな特徴です。
ここではまず、オウンドメディアとSEOの関係、そして近年注目が高まっている背景を整理します。
1-1. オウンドメディアとSEOの関係性
オウンドメディアとは、自社で管理・発信するメディアを指します。たとえば公式ブログ、製品活用ガイド、ナレッジページなどが該当します。
オウンドメディアは、外部に依存せず自社で自由にテーマや構成を決められる点が強みです。そこに検索エンジン対策(SEO)を組み合わせることで、潜在顧客が抱える疑問や課題に対し、検索経由で自社メディアにたどり着いてもらう仕組みが成立します。
SEOによって検索順位が上がれば、広告費をかけずとも継続的にアクセスを獲得できます。さらに、関連するコンテンツ群を構築することで、Googleからの評価(専門性・網羅性)も高まりやすくなるため、オウンドメディアとSEOは相性の良い組み合わせといえます。
1-2. なぜいまオウンドメディアSEOが注目されているのか
近年オウンドメディアSEOへの関心が高まっているのは、マーケティング環境の変化が背景にあります。
まず、リスティング広告やSNS広告の費用対効果の悪化が挙げられます。クリック単価(CPC)が高騰する中、限られた予算内で効率的に見込み客へリーチするには、広告以外の選択肢が必要です。その選択肢の1つがSEOであり、さらに継続的に成果を得られる場としてオウンドメディアが注目されています。
また、消費者や企業担当者の情報収集行動も変化しています。検索エンジンでの下調べを経て比較検討する行動が主流となっている今、検索起点での接点作りは欠かせません。特にBtoB領域では、問い合わせ前に情報を集めて判断を進める傾向が強く、オウンドメディアでの情報提供がリード獲得に直結する場面も多くなっています。
このように、広告に頼らず、かつ検索行動に寄り添ったユーザー接点を作れる手段として、オウンドメディアSEOは再評価されています。
2. オウンドメディアSEOのメリットと役割
オウンドメディアSEOは、単に検索上位を狙う施策ではありません。継続的な集客を可能にしながら、企業のブランド価値や信頼性を高める役割も担っています。
ここでは、オウンドメディアSEOが企業にもたらす2つの代表的なメリットとして、「広告費の抑制と資産化」「見込み客獲得とブランディング」について詳しく解説します。
2-1. 広告費削減と資産化の両立が可能
多くの企業にとって、広告費はマーケティング予算の中で大きな割合を占めます。特にクリック課金型のWeb広告(Google広告、SNS広告など)は、出稿を停止すればアクセスも止まる一時的な施策です。
それに対し、オウンドメディアSEOは一度上位表示を獲得した記事が、数か月〜数年単位で継続的に集客をもたらすという大きな強みを持ちます。これは「ストック型の集客手段」として、広告とは異なる性質を持つ点です。
実例で見る広告とSEOの違い
| 指標 | リスティング広告 | オウンドメディアSEO |
|---|---|---|
| 成果の即効性 | 高い(即日で流入) | 中〜長期で効果発現 |
| 継続コスト | クリックごとに課金 | 記事制作費のみ(維持費は低コスト) |
| 費用対効果 | 短期では高いが収束 | 長期で見ると圧倒的に優れる |
| 資産性 | なし(広告停止=ゼロ) | あり(掲載継続で流入維持) |
オウンドメディアSEOは初期投資型ですが、中長期的に見ると広告以上にROI(投資対効果)に優れた施策であるといえます。予算に限りがある中小企業やスタートアップにとっては、持続可能なマーケティング基盤を築ける手段として、オウンドメディアは重要な存在です。
2-2. 検索流入による見込み客獲得とブランディング
オウンドメディアSEOのもう1つの大きなメリットは、質の高い見込み客(リード)を、広告なしで獲得できる点です。
■検索行動の“質”が高い理由
検索エンジン経由で自社メディアにたどり着くユーザーは、自発的に課題を調べているため、関心や意欲の高い状態にあります。
たとえば「SaaS導入 比較」「採用サイト 成功事例」といったキーワードで流入してきた読者は、すでにサービス導入や情報収集のフェーズにある可能性が高く、CV(問い合わせ・資料請求)にもつながりやすいです。
オウンドメディアSEOは「顕在層」や「準顕在層」にリーチしやすく、高確度な見込み客を効率よく獲得できる手段となります。
■情報発信を通じた信頼獲得・ブランド構築
もう1つ見逃せないのが、「ブランディング効果」です。
専門的かつ有益な情報を継続的に発信している企業メディアは、ユーザーから“信頼できる会社”として認識されやすくなります。
たとえば、以下のような印象形成が期待できます。
- 「この会社は業界に詳しい」
- 「提案が的確そう」
- 「専門知識に基づいたサービスを提供していそう」
認知の積み重ねは、サービス比較時や検討段階における指名検索や想起につながり、最終的な選定理由にもなります。実際、オウンドメディア経由のCVは「他社と比較したうえで、御社が信頼できそうだった」といった理由で獲得に至るケースも少なくありません。
オウンドメディアSEOは、広告費を削減しながら高い質のユーザーにアプローチできる、極めてコストパフォーマンスの高い施策です。さらに、自社の専門性を伝えるプラットフォームとして、信頼やブランド価値の向上にも直結します。
単なる集客手段を超え、企業活動全体を支えるメディア戦略としても活用できるのが、オウンドメディアSEOの真の価値といえるでしょう。
3. オウンドメディアSEOの基本戦略
オウンドメディアSEOを成功に導くためには、「とりあえず記事を書く」という姿勢では不十分です。大切なのは、誰に向けて、どのような情報を、どんな意図で届けるかを明確にしたうえで、サイト全体を設計・運用することです。
ここでは、オウンドメディアSEOに欠かせない3つの基本戦略として、以下の要素を順に解説します。
3-1. ターゲット設計とペルソナの明確化
SEOコンテンツの起点は、「誰に向けて書くのか」という設計です。ターゲットが不明確なままでは、的外れなキーワードを選んだり、検索意図とずれた内容になったりしてしまいます。
そのため、まずはペルソナ(具体的な読者像)を明文化することが必要です。たとえば以下のような視点で、想定読者の属性・関心・悩みを細かく設計していきます。
- 年齢・性別・職業・役職(例:30代・男性・中小企業の経営者)
- 抱える課題(例:採用に苦戦している、営業の仕組みを見直したい)
- 情報収集の行動(例:Google検索を使い、自力で比較検討する)
- 意思決定までの流れ(例:情報収集→導入検討→上司提案)
ペルソナを明確にすると、検索されやすいテーマやキーワード、読者が求める表現のトーンや構成も自然に決まってきます。
3-2. カスタマージャーニーに基づくキーワード戦略
ペルソナを設計したら、次に行うのがキーワード戦略です。特に意識したいのが「カスタマージャーニー」と呼ばれる購買・導入までの意思決定プロセスです。フェーズごとに検索ニーズは異なるため、それに合わせたキーワードとコンテンツを配置する必要があります。
フェーズ別の検索意図例
| フェーズ | 検索意図の例 | コンテンツ例 |
|---|---|---|
| 認知・課題発見 | 採用がうまくいかない原因を知りたい | 「応募が来ない原因とは?」 |
| 情報収集 | 解決策を調べたい | 「採用サイトを改善する方法」 |
| 比較検討 | サービスを比べたい | 「採用管理ツール 比較・選び方」 |
| 意思決定 | 導入や相談をしたい | 「採用サイト制作 おすすめ会社」 |
フェーズに合わせてキーワードを分類・配置していくことで、あらゆる読者ニーズに対応したメディア構成が可能になります。BtoB領域では、認知から問い合わせまでの期間が長いため、複数のタッチポイント(記事)を用意して、ナーチャリングにつなげることが重要です。
3-3. E-E-A-Tを意識したコンテンツ制作方針
検索上位を目指すには、Googleの評価基準である「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」を意識したコンテンツ設計が不可欠です。なかでも、医療・金融・法律などのYMYL領域では、E-E-A-Tに欠ける記事は上位表示されにくくなっています。
E-E-A-Tの実践ポイント
| 要素 | 実装方法 |
|---|---|
| 経験(Experience) | 実体験・導入事例・ユーザーの声を記載 |
| 専門性(Expertise) | 専門部署や資格保有者による執筆・監修 |
| 権威性(Authoritativeness) | 社会的実績や第三者メディアでの掲載歴を示す |
| 信頼性(Trustworthiness) | 根拠・出典の明記、著者情報の記載、運営会社ページの整備 |
最近は、「誰が書いたのか」「どんな立場で書いているのか」が重視される傾向にあります。そのため、記事内に著者紹介や会社情報を掲載する、構造化データを使って明示する、といった基本対策も忘れず実施しましょう。
出典:Google検索セントラル「品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加」
4. SEOに強いオウンドメディアを作る方法
オウンドメディアSEOで成果を出すには、コンテンツの質だけでなく、Webサイト全体の構造や内部設計がSEOに適していることも重要です。
以下では、SEO効果を最大化するための実践的な4つのステップを紹介します。
4-1. (1)情報設計・カテゴリ構成の最適化
最初に行うべきは、サイトの情報設計です。どんなに質の高い記事を作っても、テーマごとに整理されていなければ、Googleにもユーザーにも理解されにくくなります。
重要なのが「カテゴリ構成」です。記事を無計画に追加していくと、テーマの重複や分類のブレが生じ、結果としてドメイン内の専門性評価が分散してしまいます。
実践ポイント
- カテゴリは3~6つ程度に絞る(例:「採用」「営業」「ブランディング」など)
- 各カテゴリごとに“ピラーページ”(総合的な基礎記事)を用意し、その周辺に詳細記事を配置する「トピッククラスターモデル」を採用する
- URL構造を整理する(例:/media/seo/内部対策 など)
情報設計・カテゴリ構成を最適化することで、Googleに対しても「このサイトは◯◯分野に強い」と伝えやすくなり、ドメイン全体の評価が高まりやすくなります。
4-2. (2)タイトル・見出し・メタ情報の設計
SEOにおいては、ページ単位の要素も極めて重要です。なかでもタイトルタグ(title)と見出し(H1〜H3)、メタディスクリプションは検索順位やCTRに直接影響します。
タイトル設計の基本
- キーワードは左寄せで含める(例:「オウンドメディアSEOの成功方法とは?」)
- 32文字以内で簡潔にする
- 読者のベネフィットを明示(例:「〜の方法」「〜の理由」など)
メタディスクリプションの設計
- 検索意図をくみ取り、120文字以内で要約する
- クリックを促す表現する(例:「今すぐチェック」「事例つきで紹介」など)
また、H2やH3といった見出しタグは、論理構造に沿って階層的に設計し、読みやすさとSEO評価の両方に配慮しましょう。
4-3. (3)内部リンク・構造化データの整備
SEO評価は単一ページではなく、サイト全体の構造や記事同士の関連性を含めて判断されます。そのため、記事同士をつなぐ「内部リンク」や「構造化データ」の整備が欠かせません。
内部リンクの設計ポイント
- ピラーページから子記事にリンクし、子記事からもピラーページに戻す構成
- 関連性の高い記事同士を相互リンクでつなぐ
- パンくずリストを導入して階層構造を明示
また、FAQやレビュー、著者情報などには構造化データ(Schema.org)を活用することで、Googleの理解度が高まり、検索結果にリッチリザルト(拡張表示)を出せる可能性が高まります。
4-4. (4)CMS選定とSEO対応テーマの導入
サイト構築にはCMS(コンテンツ管理システム)の選定が必要で、特にWordPressはSEO対策との相性が良く、多くの企業が導入しています。ただし、テーマやプラグインの選び方次第で表示速度や構造が大きく変わるため注意が必要です。
推奨事項
- SEO対応テーマを使用(例:SWELL、THE THOR、SANGOなど)
- 基本プラグインの導入:All in One SEO、XML Sitemap、Cacheプラグインなど
- モバイルフレンドリー・Core Web Vitals対応のチェック
LCP(Largest Contentful Paint)やCLS(Cumulative Layout Shift)などのページ表示スピードに関する評価指標は、SEO順位に影響を与えるため、軽量なテーマと最適化された画像圧縮の導入は必須といえます。
5. 記事コンテンツの制作と改善手法
SEOに強いオウンドメディアを構築したら、次に求められるのが実際の記事コンテンツの質と改善力です。どれだけ構造が整っていても、ユーザーの検索意図に合致しないコンテンツでは上位表示もCVも望めません。
以下では、記事制作における基本の考え方から、改善・運用の実践手法までを4つの観点から解説します。
5-1. 読者の検索意図に応える記事の書き方
SEO記事で最も重視すべきは、「検索意図にどこまで応えているか」です。たとえば「Web面接 服装」というキーワードで上位を狙う場合、単に「スーツがおすすめ」と述べるだけでは不十分です。読者が本当に知りたいのは以下のようなことかもしれません。
- リクルートスーツで問題ないか
- ネクタイやメイク、背景はどうすべきか
- 男性・女性でマナーが違うのか
つまり、キーワード=読者の「問い」であり、記事はその問いへの「答え」を具体的かつ網羅的に返すものであるべきです。そのためには、以下の点を意識するとよいでしょう。
- 1記事1テーマを貫く
- 見出しごとに1つの検索意図に対応させる
- 冒頭で結論を提示し、その後に根拠・事例・補足を展開する
- 実体験や一次情報をできるだけ含める
上記を意識することにより、読者満足度が高くなるだけでなく、Googleの評価軸であるE-E-A-Tにも好影響を与えられます。
5-2. 構成案・設計書の作成ポイント
記事制作の質は、執筆前の「構成」によって8割が決まるといっても過言ではありません。SEOを意識した記事構成では、以下の流れで設計するのが基本です。
構成作成の手順
- ターゲットと検索意図を明確にする
- 主要キーワードと関連語を抽出(サジェスト、再検索ワードなど)
- 見出し構成(H2・H3)を決定
- 導入文の役割を明確に(共感+結論+読むメリット)
- CTAや導線を意識した構成にする
特にH2見出しは、検索意図を分解した単位で配置するのが原則です。また、H3は具体例や対策など、より粒度を細かくして読者理解を深める役割を持たせます。
さらに、YMYLジャンルでは医学的・法律的な裏付けや出典情報の明示が求められるため、構成段階でエビデンスの挿入箇所も設計しておくことが重要です。
5-3. 初期記事・リライト・ABテストによる改善サイクル
一度記事を公開して、それで完成ではありません。オウンドメディアSEOでは、初期公開 → 検索順位・CTRの確認 → リライト → 再検証という改善サイクルを回すことで、継続的な成果を目指します。
改善サイクルの例(リライト対象の判断基準)
- 掲載3か月後の検索順位が11〜30位圏内:テコ入れのチャンス大
- CTRが1%未満のタイトル:タイトル改善を検討
- CV率が低い記事:CTA配置や導線の見直し、UI改善
改善内容としては、以下のような施策が有効です。
- 構成の見直し(より検索意図に即す形に)
- タイトル・ディスクリプションのリライト
- 見出しの強化(H2→H3分割、要点の明示)
- ABテストによるCTA配置・表現の比較検証
5-4. YMYL領域における注意点と品質担保
医療・健康・金融・法律などの分野では、いわゆる「YMYL(Your Money or Your Life)」に該当するため、特に高い品質と信頼性が求められます。
YMYL記事の注意点
- 医師・専門家・士業などの監修体制の明示
- 著者情報の公開(経歴・保有資格)
- 出典の明記(政府・学会など一次情報ソース)
- 推奨表現の慎重な選択(例:「治る」「完治する」はNG)
Googleは2022年以降、YMYL領域でのランキング評価において実績・信頼・経験の裏付けをさらに重視しており、内容が同じでも「誰が書いたか」「どこが運営しているか」で大きく順位が変動します。
そのため、記事そのものの設計だけでなく、監修者選定や編集体制の整備もメディアとしての品質担保に欠かせません。
6. 運用フェーズで押さえるべきSEO施策
オウンドメディアSEOは、公開して終わりではありません。公開後の運用こそが成果を左右するフェーズです。継続的に効果を出すためには、ユーザー行動や検索順位の変化をもとに施策を見直し、アップデートし続ける必要があります。
ここでは、運用フェーズにおいて特に重要な4つのSEO施策を解説します。
6-1. Googleサーチコンソール・GA4でのデータ分析
まず基本となるのが、数値に基づいたメディア運用です。Googleサーチコンソール(GSC)とGoogleアナリティクス4(GA4)を用いることで、検索パフォーマンスやユーザーの行動を可視化できます。
サーチコンソールで確認すべき指標
- 平均掲載順位と変動傾向
- クリック率(CTR)
- クエリごとの表示回数と流入数
- 検索パフォーマンスの低下や上昇傾向のある記事
これにより、「順位は高いのにクリックされない=タイトルの改善余地がある」「CTRは良いがCVしない=導線改善が必要」といった具体的なアクションが見えてきます。
GA4で確認すべき指標
- 直帰率・離脱率
- スクロール率・平均滞在時間
- ページ別CV数とその導線
GSCとGA4を組み合わせることで、検索流入→コンテンツ接触→CVという一連のユーザー行動を把握し、ボトルネックの特定と改善施策立案が可能になります。
6-2. CVにつなげる導線設計とUI改善
SEOで流入を集めるだけでは成果とはいえません。大切なのは、記事を読んだ先にある「次の行動(=コンバージョン)」に自然につなげる設計です。
よくある導線設計の課題
- CTA(問い合わせ・資料DL)の設置が目立たない/唐突すぎる
- 記事内容とCTAが一致していない
- スマホ表示でCTAが見えづらい、ページが重い
改善の方向性
- 記事下部に関連記事やピラーページへのリンクを設置し、回遊性を高める
- CTAは内容と関連性のあるものを文脈内で自然に配置
- ボタンの色・文言・配置位置をABテストして最適化
- フォームの入力項目は可能な限り削減し、離脱を防止
また、UI改善はUX向上だけでなく、Googleの評価にも関わるページエクスペリエンス指標(Core Web Vitals)に直結するため、技術的改善も並行して行うことが望ましいです。
6-3. 自然な被リンク獲得とSNS連携
外部からの被リンク(バックリンク)は、現在でもSEOにおいて重要なランキング要素の1つとされています。とはいえ、意図的にリンクを集めることはリスクを伴うため、自然な拡散を促す設計が必要です。
被リンクを得るための工夫
- 業界の統計データや一次情報を含んだ「シェアされやすい」記事を用意
- SNSやメルマガでの拡散を前提とした「タイトル設計」「サムネイル設計」
- 自社サービスの活用事例など、他社が引用しやすい構成や内容にする
また、X(旧Twitter)やLinkedIn、noteなどターゲット層が集まるSNSと連携し、記事の露出機会を増やす施策も、SEOと連動する動きとして重要です。
UGC(ユーザー生成コンテンツ)との接点を作ることで、信頼性と話題性の両方が向上し、自然リンクの獲得につながります。
6-4. 定期的なリライトと順位チェックの習慣化
コンテンツは一度作って終わりではなく、検索結果やニーズの変化に合わせてリライト・最適化し続けることが重要です。
リライトの判断基準
- 順位が11〜30位で横ばいの記事
- 以前より順位・CTRが落ちている記事
- 検索クエリに対する網羅性や新鮮さに欠ける内容
リライトの具体策
- 情報更新:最新情報や制度改正の反映
- 構成改善:検索意図と合致するよう見出しを変更
- 内容追加:不足している観点を補強、図表を追加
- タイトル見直し:CTR改善のための文言調整
また、リライトは“過剰に行わない”こともポイントです。安定して上位を取れている記事は、触らずに保守運用とする判断も重要になります。
7. オウンドメディアSEOの失敗例と回避策
オウンドメディアSEOは、うまく運用すれば中長期的に高い成果を上げられる施策ですが、戦略や運用体制を誤ると、時間と労力をかけても結果が出ない事態に陥ることもあります。
以下では、よくある失敗パターンを3つ紹介し、その原因と回避策を解説します。
7-1. キーワード戦略なしに記事を量産したケース
最も多い失敗の1つが、キーワード設計をせず「なんとなく話題になりそうなテーマ」で記事を量産してしまうパターンです。
実例
- 「社内の成功事例を紹介しよう」と決めたが、検索される見込みがないテーマだった
- ペルソナや検索フェーズを考慮せず、浅く広い記事ばかりを制作
- カテゴリ構成がバラバラで、専門性がGoogleに伝わらなかった
回避策
- 記事制作前に必ずキーワード調査・検索意図分析を実施する
- GoogleサジェストやPeople Also Ask(関連質問)を活用する
- コンテンツ設計にはカスタマージャーニーに沿った構成表を作成する
7-2. 更新が止まり評価を落とした例
せっかく構築したオウンドメディアでも、更新が止まると検索順位が徐々に下がっていく傾向があります。特にYMYLジャンルでは、情報の鮮度が信頼性に直結するため、放置されたメディアは評価が下がりやすいです。
実例
- ソース不足で半年以上更新が止まる
- 最新情報への更新が行われず、読者からの信頼を損なう
- Googleから「死んだサイト」と見なされる
SEOは継続性が評価に大きく関わるため、「定期更新されているか」「最新情報を反映しているか」は明確な評価軸の1つです。
回避策
- 月1〜2本以上の更新計画を立て、必ず運用担当を明確にする
- 検索上位を維持している記事でも、更新日と中身を見直す体制を組む
- 「新着情報」「更新履歴」をサイト内に設置し、更新の継続を示す
7-3. 社内体制やリソース不足による失敗要因
戦略・設計が正しくても、社内体制が整っていないと運用が続かず、結局失速してしまうケースも多々あります。
実例
- 執筆・更新がすべて1人に属人化しており、稼働が止まるとコンテンツ制作も止まる
- 担当者がSEOに詳しくなく、改善の手が打てない
- 経営層からの理解が得られず、予算もリソースも不十分
オウンドメディアSEOは「一人で完結する仕事」ではありません。編集・執筆・分析・改善をチームで連携し、継続的に動かせる体制が不可欠です。
回避策
- 社内でディレクション・執筆・SEO分析の役割分担を明確にする
- 外注(記事制作・分析)も視野に入れた体制設計
- 経営層向けに「成果の可視化資料」を定期提出し、予算確保のための理解促進を図る
8. 成功企業の事例に学ぶSEO運用の工夫
オウンドメディアSEOの成果を最大化するためには、理論だけでなく、実際に成功している企業の実践事例から学ぶことが非常に有効です。以下では、業種や目的の異なる3社の成功事例を通じて、それぞれがどのような工夫や戦略を用いてSEO成果を出しているかを紹介します。
8-1. 事例1:BtoB企業が月間10万PVを達成した戦略
あるBtoB系のSaaS企業では、「業務改善」「業務効率化」「DX」など、導入検討層が検索しやすいキーワードを中心にコンテンツを構築。約2年間で月間10万PVを超える規模にまでオウンドメディアを成長させました。
成功要因
- ターゲットに刺さる業務課題起点のキーワード戦略を徹底
- 初期フェーズでは“認知〜情報収集”層向けの記事を優先的に制作
- ホワイトペーパーへの導線設計を全記事に組み込み、CVを最大化
- 四半期単位でアクセス・CVデータを元に記事カテゴリの比重を調整
また、上位記事は半年ごとに必ず情報更新(リライト)を実施し、検索結果での鮮度と信頼性を担保していました。継続的PDCAと社内外の連携体制が、SEO効果とCV率の両立を実現しています。
8-2. 事例2:中小企業が指名検索を増やしたコンテンツ設計
地方の人材系企業では、大手と比べて広告予算が限られる中、“地域密着×専門分野”に特化したオウンドメディアを構築。競合の少ないロングテールキーワードを中心に、月間3万PV・指名検索の増加を実現しました。
成功要因
- 「福岡×介護職」「地元×採用支援」など、地域名+専門領域でニッチを攻めた
- 地域の支援制度や求人事情をテーマにした“役立つ情報メディア”としての信頼獲得
- 1記事ごとに「運営会社=専門性がある」という信頼感を設計
- SNSと連携し、記事→無料セミナー→問い合わせという接点を多層的に設計
商圏を絞り込んだ情報提供で、SEOだけでなく企業のブランド認知を高め、問い合わせ時の信頼形成にも成功しました。
8-3. 事例3:SaaS系企業がCVを最大化した記事導線
SaaSツールを提供するスタートアップ企業では、CVを最大化するためにメディア全体を「リード獲得のための設計図」として構築していました。流入記事から、比較コンテンツや事例コンテンツに回遊させることで、CVまでのナーチャリングがスムーズに行われています。
成功要因
- 初期流入記事(例:「業務自動化 方法」)→中間コンテンツ(比較・導入事例)
- 記事内に配置されたCTAは、「無料診断」「事例ダウンロード」など読者のフェーズに合ったものを複数用意
- 成果記事の導線や配置は定期的にABテストを実施し最適化
- GA4とCRMを連携し、どの記事が商談に最もつながったかを可視化
→CTA記事 という回遊フローを徹底的に設計
結果として、PV数は月間1.5万程度ながら、問い合わせ数は月100件以上、CV率は平均3.5%超を維持しています。
9. オウンドメディアSEOの効果測定とKPI設計
オウンドメディアSEOは、中長期的な取り組みであるがゆえに、「どのように効果を測るか」「何を目標とするか」が曖昧になりがちです。しかし、明確な指標がなければ、施策の良否を判断できず、改善も進みません。
最後に、SEOにおける定量的な評価方法と、適切なKPI設計の考え方を解説します。
9-1. PVだけでなく「CV・問い合わせ数」をKPIにする
オウンドメディアの運用では、PV(ページビュー)やUU(ユニークユーザー)といったアクセス指標が重視されがちです。確かに流入数はSEOの成果を把握するうえで重要な指標ですが、それだけではビジネスへの貢献度を正しく測れません。
真に重要なのは、その流入が「問い合わせ」や「資料請求」「製品の認知」など、実際のビジネスゴールにつながっているかどうかです。特にBtoBにおいては、流入数が少なくても高いCV率を誇る記事やカテゴリが存在するため、“数”だけではなく“質”を見る視点が必要です。
たとえば、月に500PVしかないがCVが20件ある記事と、1万PVあってもCVが1件しかない記事とでは、後者のほうが一見成果がありそうに見えても、実際のビジネス貢献度は前者が上回る可能性が高いといえます。
9-2. 中長期視点での評価指標とマイルストーン
SEO施策は、公開してすぐに結果が出るものではありません。特にオウンドメディアは資産型の施策であり、半年〜1年単位での継続運用を前提にKPIを設定する必要があります。
初期フェーズでは、月間PVや掲載順位の上昇を主要KPIとし、徐々に「CV数」や「CVR(コンバージョン率)」へと移行していくのが基本的なステップです。
評価タイミングとしては、以下のようなマイルストーンを設けておくと進捗管理がしやすくなります。
- 公開から1か月:インデックス状況・平均掲載順位を確認
- 公開から3か月:上位表示(10〜20位)を目標に
- 公開から6か月:CV発生・問い合わせ件数の変化を計測
- 公開から12か月:戦略全体の見直しとカテゴリ単位での強化判断
フェーズごとに適切な評価指標を切り替えることで、「いま何を重視すべきか」が明確になり、組織としての合意形成も取りやすくなります。
9-3. 外注との連携や運用体制の整備
社内だけでメディアを運営する場合でも、記事制作・SEO分析・ディレクションなどの業務が属人化してしまうと、継続性や品質の維持が難しくなります。特にKPIの数値管理や改善アクションを回していくには、定量評価を共有・実行できる体制の整備が大事です。
このとき、外注パートナー(記事制作会社、SEOコンサルなど)と連携する場合は、単なる記事発注者としてではなく、「共に目標を追う伴走者」としての関係を築くことが成功につながります。
たとえば、以下のような連携設計が有効です。
- 四半期ごとのKPI進捗報告を行い、達成状況を共有
- GSCやGA4の管理画面を共有し、データドリブンな提案を求める
- 改善方針の擦り合わせを定期的に行い、「指示待ち」ではない関係性を作る
また、メディア全体として「どこに注力すべきか」を判断するには、KPI単位でのカテゴリ管理(例:「SEOカテゴリ」「採用カテゴリ」ごとのCV・UUの比率)も有効です。
このような設計ができれば、限られた予算・リソースでも、より費用対効果の高い運用が可能になります。
まとめ
オウンドメディアSEOは、単なる記事作成や検索順位向上を目的とするのではなく、中長期的に見込み顧客との接点を築き、信頼を獲得しながら継続的なビジネス成果につなげる戦略的施策です。
そのためには、ターゲットや検索意図に基づいたコンテンツ設計、サイト構造の最適化、継続的な運用と改善が欠かせません。また、短期的なPVや順位に一喜一憂するのではなく、問い合わせやCVといった“事業貢献度”を軸にKPIを設計することが、運用体制の安定にも直結します。
すぐに成果が出る施策ではありませんが、適切な戦略と体制のもとで運用を続ければ、広告に頼らず見込み客を集める“資産”として、企業に大きな価値をもたらすのがオウンドメディアSEOです。
当記事を参考に、貴社のメディア運用を見直し、持続的に成果を生むマーケティング基盤の構築を目指してみてください。