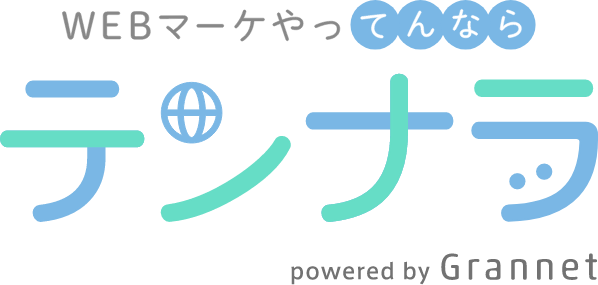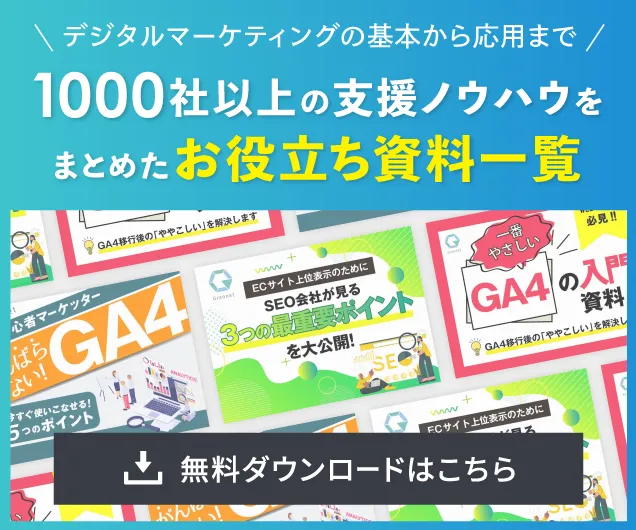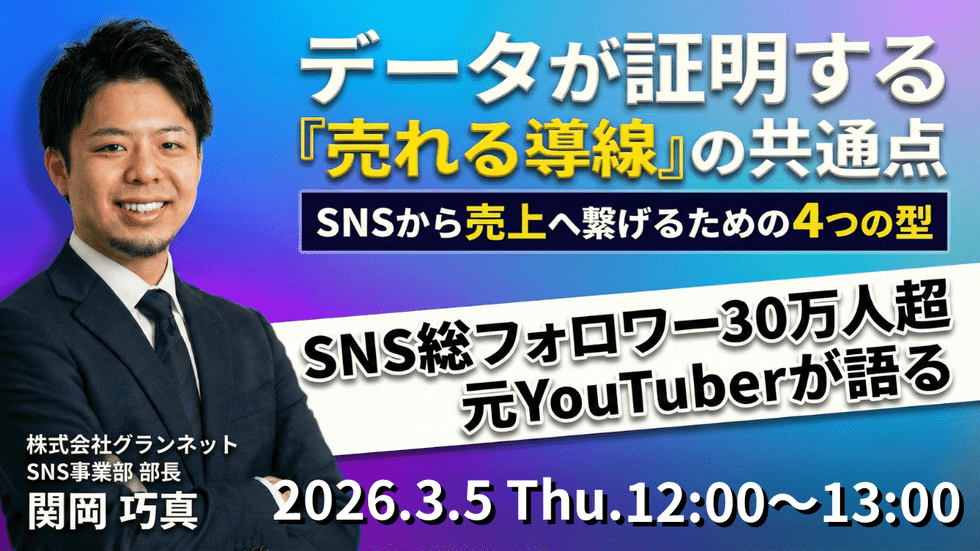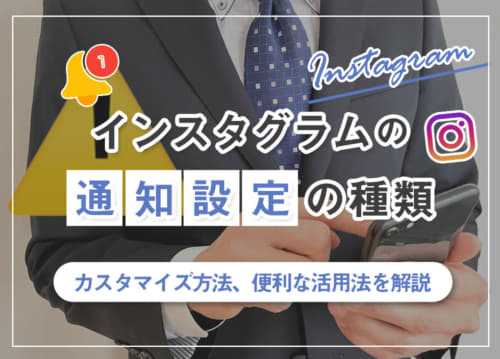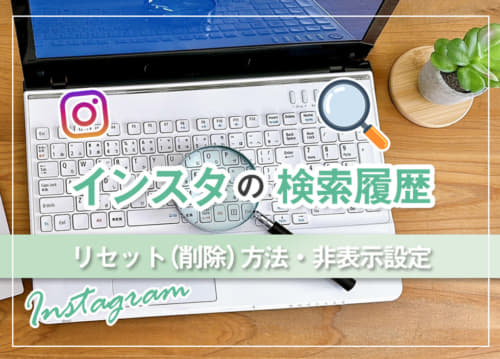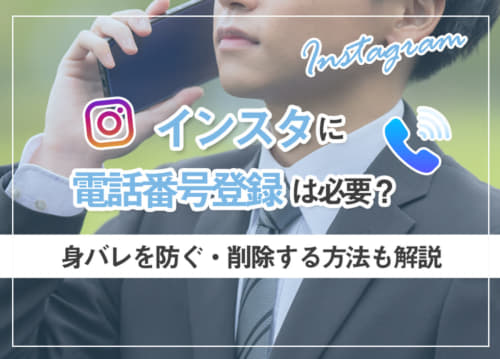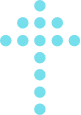seo競合調査では何をする?調査方法・役立つツール・注意点を紹介
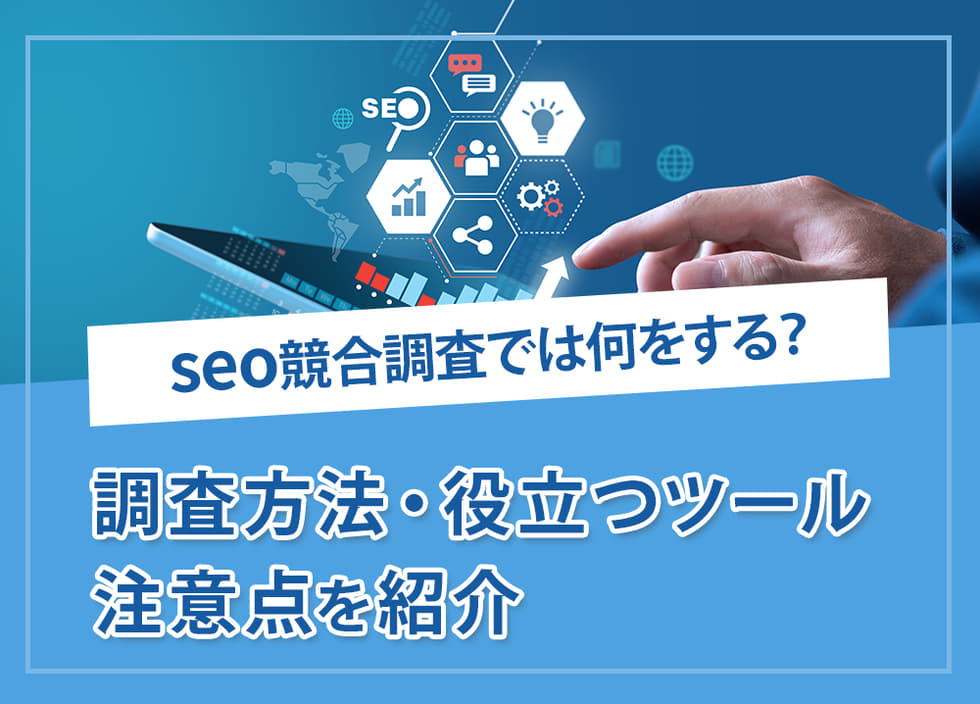
SEO競合調査は、検索結果で上位を争うサイトを分析し、自社の改善点や差別化戦略を導き出すために欠かせないプロセスです。正しい方法で行えば、検索意図の把握やE-E-A-Tの強化、外部施策の最適化など、多角的な改善が可能になります。
当記事では、競合調査の目的や何をすればいいのか、具体的な手順とチェックポイント、便利なツール、そして調査結果をSEO戦略に落とし込む方法までを詳しく解説します。
1. SEO競合調査とは?
SEO競合調査とは、検索エンジンの上位表示を狙ううえで、自社と同じキーワードを対象にしているサイトを分析し、改善のヒントや戦略を導き出すプロセスです。単なる順位チェックではなく、競合が行っている施策や強み・弱みを把握し、自社のSEO施策に反映することが目的です。
ここでは、競合の定義と調査によって得られる効果について解説します。
1-1. SEOにおける競合の定義
SEO競合調査における「競合」とは、業種やビジネス形態を問わず、検索結果で同じキーワードを狙う全てのサイトを指します。たとえばSEO関連のキーワードでは、コンサルティング会社、ツール提供企業、個人ブロガーなどが入り混じることがあります。
重要なのは「業界内のライバル」だけではなく、「検索結果のクリックを奪う存在」も調査対象になるという視点です。
1-2. 競合調査の目的と得られる効果
競合調査を行うことで、自社の施策に活かせる多くの情報が得られます。
- 上位表示されている理由や成功パターンを把握できる
- 自社の弱点や改善すべきポイントが明確になる
- 差別化すべき要素や独自性の方向性が見えてくる
これらを継続的に把握することで、アルゴリズムの変化や市場動向に素早く対応でき、長期的な集客力向上につながります。
2. SEO競合調査で何をすればいいのか
SEO競合調査は、目的を明確にし、手順を踏んで行うことが重要です。闇雲にデータを集めても、戦略に結びつけられなければ意味がありません。
ここでは、調査の基本的な流れと、競合サイトを選ぶ際の考え方について説明します。
2-1. 調査の基本的な流れ
SEO競合調査で「何をすればいいのか」が分からない場合、多くの方が最初につまずくのは「何から手を付けて良いのか分からない」という点です。そこで重要なのが、最初に全体の流れを理解しておくことです。
競合調査は、感覚的に気になるサイトを眺めるだけでは効果が薄く、必ず一定の手順を踏んで進める必要があります。以下は、実務でよく用いられる基本のステップです。
・対象キーワードの決定
まずは調査対象とするキーワードを明確にします。メインキーワードに加え、関連性の高いロングテールキーワードも洗い出すことで、幅広い検索結果を比較できます。
例:「seo競合調査」をメインに、「seo競合調査 方法」「seo競合調査 何をすればいい」「seo競合調査 チェック」などの派生語も含めて調査対象にします。
・競合サイトの抽出
Google検索で対象キーワードを入力し、検索上位10〜20サイトをリスト化します。このとき、広告枠やニュース枠を除き、自然検索の結果を優先して抽出します。また、PCとスマホで結果が異なる場合があるため、両方で確認するのが望ましいです。
・各サイトの分析
コンテンツの網羅性、文章構成、見出しの工夫、内部リンク構造、被リンク状況、表示速度、モバイル対応などを多角的にチェックします。単に「文字数が多い/少ない」ではなく、情報の質や検索意図との一致度も評価します。
・比較表の作成
競合サイトの分析結果を一覧化し、自社サイトと比較します。このとき、強み・弱みを明確に記載することで、改善の優先度が見えやすくなります。ExcelやGoogleスプレッドシートを使うと、施策の整理と共有がしやすくなります。
・改善施策の立案
比較表から導き出した改善点を、短期でできる修正(例:見出しの調整、内部リンク追加)と、中長期的に取り組む改善(例:新規コンテンツの追加、被リンク獲得施策)に分けます。これにより、施策の実行スケジュールが組みやすくなります。
2-2. 競合サイトの選び方|直接競合と間接競合
SEO競合調査で対象とするサイトを間違えると、分析結果が戦略に活かせません。ここでは、選定時の基本的な考え方を押さえておきましょう。
1. 直接競合
同じ業種・サービスを提供し、同じ顧客層を狙うサイトです。たとえば、SEO会社AとSEO会社Bが同じ「SEO競合調査」というキーワードで集客を狙っている場合、両者は直接競合にあたります。
直接競合はサービスやコンテンツ構成が似ているため、差別化ポイントを見つけやすいというメリットがあります。
2. 間接競合
業種は異なるものの、同じ検索キーワードで上位を取っているサイトです。
例えば、SEOツール提供企業のブログ記事や、個人運営のSEOノウハウサイトなどは、商材が異なっても検索結果上では顧客のクリックを奪う存在になります。
間接競合は見落とされがちですが、実はユーザーの行動を大きく左右する存在です。直接競合の施策に加え、間接競合が提供している切り口やコンテンツ形式を参考にすることで、新しい差別化戦略を見つけられます。
3. SEO競合調査の主な方法
SEO競合調査は、「キーワード」「コンテンツ」「外部要因」「技術要因」の4つの観点から行うと抜け漏れが少なくなります。ここでは代表的な方法を紹介します。
3-1. キーワード順位と検索意図の分析
対象キーワードでの検索順位を確認するのは基本ですが、単に順位を見るだけでは不十分です。
特に重要なのは検索意図の把握です。上位表示されているコンテンツが、ユーザーのどんなニーズに応えているのかを分析します。検索意図は以下の3タイプに分類されます。
- 情報収集型(Informational):知識や方法を知りたい
- 取引型(Transactional):購入や契約、申し込みをしたい
- 案内型(Navigational):特定のサイトやブランドにアクセスしたい
検索意図の種類によって、適切なコンテンツ形式(解説記事、比較表、事例集など)が変わります。競合の順位と合わせて意図を把握することで、自社コンテンツの方向性がより明確になります。
3-2. コンテンツ構成・テーマ・更新頻度の確認
競合ページの見出し構成や網羅性、情報の深さを分析します。単なる長文ではなく、見出しの切り方や情報の優先順位が検索意図と一致しているかをチェックすることが大切です。
また、更新頻度や最新情報の反映具合もGoogleの評価に影響します。特にSEO関連のテーマは変化が早いため、古い情報のまま放置されている競合はチャンスといえます。
3-3. 被リンクとドメイン評価のチェック
外部サイトからの被リンクは、検索順位に大きく影響する要素の1つです。
AhrefsやSEMrushなどのツールを使えば、競合がどのようなサイトからリンクを獲得しているかを確認できます。リンク元が業界関連の高品質サイトであれば、Googleからの評価も高くなる傾向があります。
併せて、ドメイン評価(DRやDAなどのスコア)を確認することで、競合全体のSEO基盤の強さを把握できます。
3-4. サイト構造・内部リンク・表示速度の確認
競合サイトの内部リンク構造やカテゴリー設計、パンくずリストの有無は、ユーザーの回遊性や検索エンジンのクロール効率に直結します。
また、表示速度やモバイル対応はユーザー体験(UX)に影響し、離脱率にも関わります。PageSpeed Insightsなどの無料ツールを使って、速度スコアや改善提案を確認するとよいでしょう。
4. 競合調査でチェックすべきポイント
SEO競合調査は、単に競合のやり方を真似するためのものではなく、自社サイトに不足している要素を特定し、改善方針を立てるための工程です。
調査項目は幅広くありますが、すべてを同じ優先度で確認していては時間がかかりすぎます。ここでは、特に成果に直結しやすい3つの視点に絞って、具体的なチェックポイントと活用例を解説します。
4-1. 検索意図との一致度と差別化要素
まず注目すべきは、検索意図に対して競合コンテンツがどれだけ応えているかです。
たとえば「seo競合調査 方法」というキーワードで検索した場合、ユーザーの多くは「調査の手順」や「ツールの活用方法」を知りたいと考えています。にもかかわらず、上位ページがツール紹介だけに偏っていれば、実践的な手順や事例を加えるだけで差別化が可能です。
検索意図との一致度を測る際は、以下のような切り口で確認します。
- 見出し構成がキーワードの意図に沿っているか
- 具体例や手順が盛り込まれているか
- 初心者でも理解できる文章構造になっているか
また、差別化要素としてはオリジナルの統計データ、業界特有の事例、図解や動画コンテンツが効果的です。競合の多くはテキスト中心のため、視覚情報や独自分析を加えるだけでも上位表示の可能性が高まります。
4-2. E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の有無
Googleの評価指標として注目されるE-E-A-T(Experience・Expertise・Authoritativeness・Trustworthiness)は、SEO競合調査でも欠かせないチェックポイントです。
実務での確認方法は次の通りです。
- 経験(Experience):実際にツールや施策を使った体験談が掲載されているか。スクリーンショットやビフォーアフター事例があれば高評価。
- 専門性(Expertise):執筆者や監修者の経歴・資格が明記されているか。特にSEOやマーケティングの資格や実績は信頼度を高めます。
- 権威性(Authoritativeness):業界での認知度や、他メディアからの引用・紹介があるか。高品質な被リンクもこの要素に含まれます。
- 信頼性(Trustworthiness):連絡先や運営会社情報、参照元リンクの明記があるか。情報源が明確であることは信頼性を大きく左右します。
自社サイトを改善する際は、これら4要素のうち不足している部分を優先的に補強します。たとえば監修者プロフィールを追加するだけでも、専門性と信頼性の両方を高められます。
4-3. 外部発信・SNS活用状況
SEOはサイト内部の最適化だけでなく、外部からの評価や流入経路の多様化も重要です。競合がSNSや外部メディアをどの程度活用しているかを調べることで、自社の集客戦略の穴が見えてきます。
チェックするポイントの例
- 記事URLをSNS(Twitter、Facebook、LinkedInなど)で定期的にシェアしているか
- YouTubeやポッドキャストなど、他メディアで同テーマを発信しているか
- SNS投稿に対する反応(いいね数・コメント数・シェア数)がどれくらいあるか
SNSからの流入は直接的なSEO評価には直結しないとされますが、間接的には被リンク獲得やブランド検索の増加につながります。たとえば、競合が記事公開後にSNSでキャンペーンを行い、多数のシェアとリンクを獲得している場合、その仕組みを参考にすることで外部施策の強化が可能です。
5. SEO競合調査に役立つツール
効率的かつ正確なSEO競合調査を行うには、適切なツールの活用が欠かせません。ツールを使うことで手作業では時間がかかる被リンク分析や流入経路の把握、検索順位の変動チェックなどを短時間で正確に行えます。
ここでは、無料と有料の代表的なツールと、その活用方法を紹介します。
5-1. 無料ツール(Google検索、キーワードプランナーなど)
無料ツールは導入コストがかからず、SEO初心者や小規模サイトの運営者でも気軽に利用できます。特に初期調査や基礎的な分析に向いています。
基本的で重要なツールです。キーワードを入力して上位サイトの傾向を確認し、検索意図やコンテンツ形式を把握します。検索結果ページ(SERP)の変化を定期的に記録することで、競合の順位推移や新規参入サイトもチェックできます。
広告用ツールですが、SEOでもキーワードの検索ボリュームや競合性の把握に役立ちます。関連キーワードの提案機能を使えば、競合がまだ狙っていないロングテールキーワードを発見できる可能性があります。
サイトの表示速度を計測し、改善ポイントを提示してくれるGoogle公式ツールです。競合サイトのURLを入力すれば、表示速度やモバイル対応状況を比較できます。
5-2. 有料ツール(Ahrefs、SEMrush、SimilarWebなど)
有料ツールは、無料ツールでは取得できない詳細データを提供します。大規模な分析や精度の高い戦略立案には欠かせません。
被リンク分析に強みがあり、競合サイトがどのような外部リンクを獲得しているかを可視化できます。また、流入キーワードやページ単位のSEO評価も確認可能です。被リンクの質と量を比較することで、自社の外部施策の優先度を判断できます。
SEOだけでなく、広告やSNS分析機能も備えた総合ツールです。競合のオーガニック流入、広告出稿キーワード、SNS発信状況などを一元的に把握でき、マーケティング全体の比較分析が可能です。
競合サイトのアクセス数や流入元(検索、SNS、リファラルなど)を推定値で確認できます。特に、検索流入とSNS流入の比率を比較することで、どの集客チャネルが強いのかが一目でわかります。
ツールは「使うこと」が目的ではなく、「得られたデータを施策に反映させること」が重要です。たとえば、Ahrefsで競合が獲得している高品質な被リンク元を見つけた場合、それらのサイトに自社コンテンツを紹介してもらえるような企画を検討する、といった具体的な行動につなげる必要があります。
6. 調査結果をSEO戦略に活かす方法
SEO競合調査は、情報を集めただけでは意味がありません。重要なのは、調査結果をもとに自社サイトの改善施策を明確化し、優先順位をつけて実行することです。
ここでは、調査データを戦略に落とし込むための基本的な流れと具体例を紹介します。
6-1. 強み・弱みの整理と優先順位付け
競合比較の結果から、自社の現状を客観的に評価します。たとえば、以下のように整理すると施策の方向性が明確になります。
強み
例:記事数が多く、特定ジャンルでの網羅性が高い/ブランド知名度があり指名検索が多い
弱み
例:被リンク数が競合より少ない/表示速度が遅い/検索意図への適合度が低い
このとき、改善項目を「短期で改善できる施策」と「中長期で取り組む施策」に分けるのがポイントです。
短期施策は見出し修正や内部リンク追加、既存コンテンツの追記など、即効性のある改善を指します。中長期施策は新規コンテンツ制作や外部施策(被リンク獲得、ブランド構築など)で、時間をかけてじわじわ成果を伸ばす領域です。
6-2. 新規コンテンツ企画と既存ページの改善
調査で得られた競合の傾向をもとに、新しいコンテンツ案を企画します。たとえば、競合が「SEO競合調査のツール紹介」だけに特化している場合、自社では「ツール+実践手順+事例紹介」をセットにした記事を制作すれば差別化が可能です。
既存ページの改善では、次のようなアプローチが有効です。
- 見出しや本文に不足している関連キーワードを追加する
- 最新情報やデータを反映して情報鮮度を保つ
- 読みやすさを高めるために表や図解を追加する
- 内部リンクを最適化し、関連ページへの回遊を促す
改善を継続的に行うことで、検索エンジンからの評価が徐々に高まり、長期的な順位向上が見込めます。
■戦略活用の成功例(簡易ケース)
あるBtoB企業では、競合調査を行った結果「記事の質は高いが、特定ジャンルのコンテンツ数が不足している」ことが判明しました。
そこで不足ジャンルの専門記事を毎月3本追加し、同時に被リンク施策を強化したところ、半年後には主要キーワードの検索順位が平均で4位→2位に改善しました。
7. SEO競合調査の注意点
SEO競合調査は正しく行えば大きな成果につながりますが、手順や視点を誤ると時間と労力が無駄になってしまいます。ここでは特に実務で陥りやすい注意点を3つ取り上げ、回避策とあわせて解説します。
7-1. 模倣だけで終わらないための視点
競合分析を行うと「この形式が上位に来ているから、同じ形で作ればいい」と考えてしまいがちです。しかし、それではGoogleに評価されにくく、ユーザーの支持も得られません。検索上位はあくまで「今の評価基準で良いとされている一例」にすぎず、将来的なアルゴリズム変更で順位が変動する可能性もあります。
参考にすべきは「構成や切り口の優れた部分」だけにとどめ、そこへ自社ならではのデータや事例、視点を加えることが不可欠です。
7-2. データの一部だけで判断しない
被リンク数、検索順位、アクセス数など、単一の指標だけを根拠に戦略を決めてしまうと、誤った方向へ進むリスクがあります。たとえば、被リンク数が多くてもリンク元の質が低ければ順位改善にはつながらないケースもありますし、順位だけを見ていてもCV(コンバージョン)につながっていない可能性もあります。
分析時は、複数の指標を組み合わせて総合的に評価することが重要です。順位・トラフィック・CV・滞在時間・直帰率などをセットで確認し、施策の優先順位を見極めましょう。
7-3. 定期的な見直しを怠らない
SEOの世界は常に変化しており、検索アルゴリズムのアップデートや競合サイトの施策によって順位は容易に変動します。一度の調査結果を基に長期的な戦略を固定してしまうと、数か月後には状況が大きく変わっている可能性があります。
最低でも四半期に一度は競合調査を実施し、現状の順位・コンテンツ傾向・被リンク状況を再確認することが望ましいでしょう。
まとめ
SEO競合調査は、単なる順位チェックではなく、競合の施策や戦略を多角的に分析し、自社の改善方針を明確にするための重要な手法です。検索意図やコンテンツ構成、E-E-A-T、外部施策などを総合的に評価し、ツールを活用することで効率と精度が高まります。
重要なのは、得られたデータを模倣で終わらせず、独自性を加えて施策化すること。定期的な見直しと継続的な改善を行い、長期的な検索順位向上を目指しましょう。