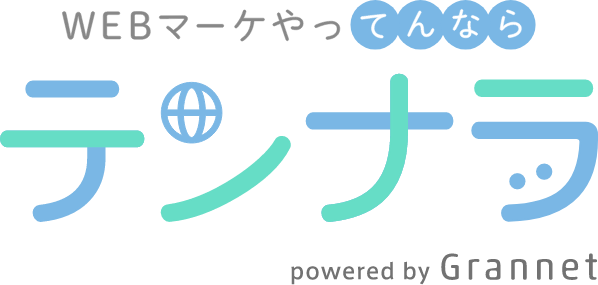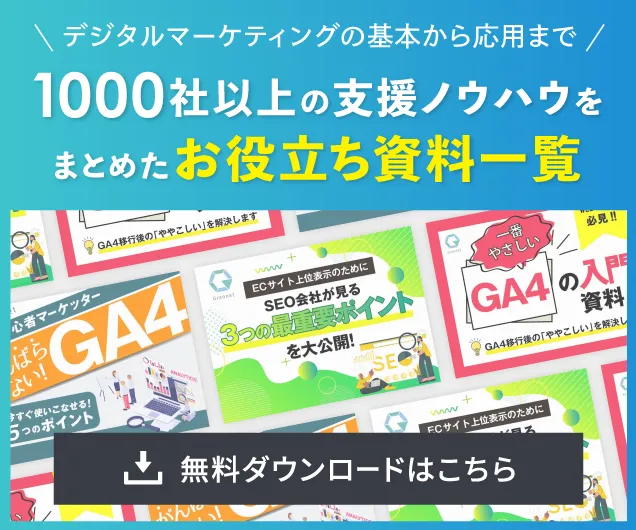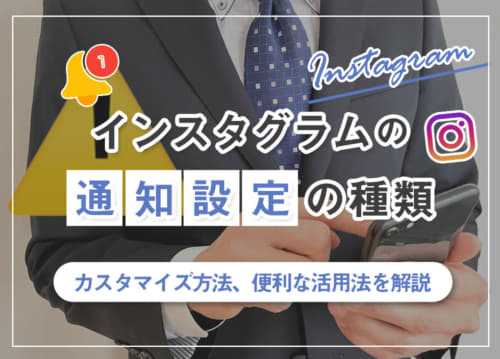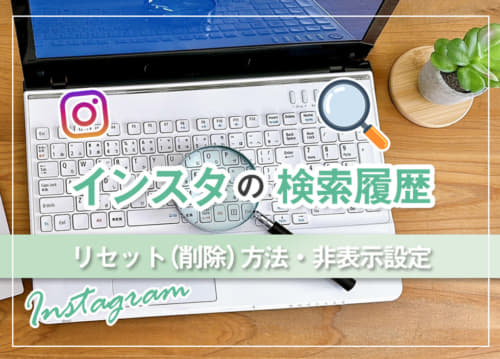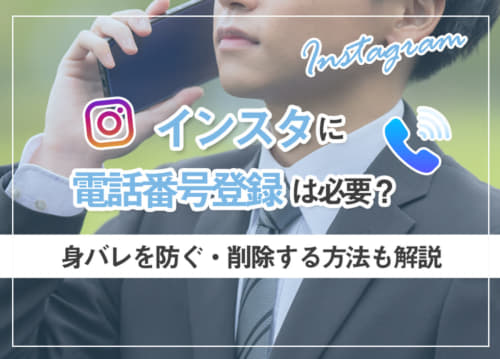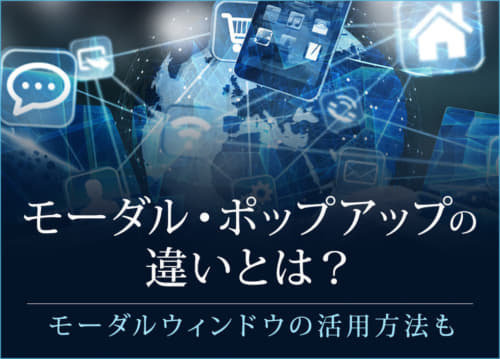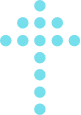Tiktok採用とは?注目される背景や導入方法や成功のポイントを解説

近年、企業の採用活動にSNSを活用する事例が増えています。なかでも若年層を中心に絶大な人気を誇るTiktokを使った「Tiktok採用」が注目されています。短尺動画が特徴のTiktokは、企業の魅力や職場の雰囲気を視覚的かつ直感的に伝えられるため、従来の採用手法にはない高い拡散力と訴求力を持っています。しかし、「具体的にどう始めればよいかわからない」と感じている方も多いでしょう。
当記事では、Tiktok採用の基本情報、Tiktok採用と相性の良い業界、注目される理由から、導入方法、成功のポイントまで詳しく解説します。
1. Tiktok採用とは?
Tiktok採用とは、動画共有プラットフォームである「Tiktok」を利用して、企業が求職者に向けた情報発信や人材募集を行う採用手法のことです。近年、従来の求人サイトや企業ホームページによる採用活動だけではターゲットとなる人材層に十分なアプローチが難しくなりつつあります。特に若年層のネット利用環境が変化し、SNSを中心に情報収集を行う傾向が強くなったことで、企業側も新たな採用手法を取り入れる必要が生じています。
Tiktok採用では、短尺の縦型動画を通じて企業のリアルな雰囲気や職場環境、働く社員の様子を視覚的に訴求できることが魅力です。言葉や写真だけでは伝えきれない社内の空気感や企業文化を、わずか数十秒の動画で効果的に伝えることができます。その結果、企業と求職者の間にミスマッチが起こりにくくなり、採用効率の向上や定着率アップにもつながります。
また、Tiktokはアルゴリズムによってユーザーの関心に合わせた動画を配信するため、企業が従来リーチしづらかった潜在的な人材層にも効率的にアプローチできるという利点があります。そのため、最近では積極的に若手採用やアルバイト採用を行う企業を中心に注目が高まっています。
1-1. Tiktok採用の基本情報と特徴
Tiktok採用の基本的な仕組みは、企業がTiktok上に公式の採用専用アカウントを開設し、社員インタビューや職場の日常、採用に関するQ&Aなど、求職者が興味を持つ内容を動画として投稿することです。これまでの採用活動では主に求人情報サイトや企業ホームページを中心にテキストや写真での発信が主流でしたが、Tiktok採用では動画を通じて「リアルさ」や「親近感」を伝えることに特化しています。
特徴としては、Tiktokの動画が縦型・短尺(15秒~60秒)であるため、ユーザーが気軽に視聴できる点があります。企業側も手軽に撮影・投稿できるため、コンテンツ制作に関する負担も比較的小さくなっています。また、エンターテインメント性の高い動画が拡散されやすく、面白さや共感を呼ぶコンテンツを発信すれば、予想以上の認知拡大効果も期待できます。
1-2. Tiktok採用の主なターゲット層と相性の良い業界
Tiktok採用が特に相性が良いのは、SNSを頻繁に利用する10代から20代の若年層を採用ターゲットとしている業界や企業です。具体的には新卒採用や若手の中途採用、さらにはアルバイトやパート採用を行う企業に特に効果的とされています。
また、業界別に見ると、飲食店や小売業といったサービス業、美容・ファッション業界、エンターテインメント業界などが挙げられます。これらの業界はTiktokのユーザー層と親和性が高く、視覚的に仕事内容や職場の楽しさをアピールしやすいため、採用活動に効果を発揮しやすいです。一方で、製造業やIT業界、一般企業でも、会社の雰囲気や人間関係、社員の日常を紹介する形で活用すれば一定の効果を期待できます。
2. Tiktok採用が注目される理由
現在、多くの企業がTiktok採用に関心を寄せています。なぜ今、Tiktokを利用した採用活動が注目を集めているのでしょうか。
ここではTiktok採用が特に注目される背景や理由について、具体的に掘り下げて解説します。採用活動においてTiktokが魅力的とされる理由を理解した上で、自社に取り入れるべきかを判断しましょう。
2-1. 若い世代の利用者が多く採用ターゲットと合致する
Tiktokが採用活動に適している最大の理由は、Tiktokユーザーの中心層が10代〜20代前半であるということです。企業が求める人材ターゲット層とTiktokのメインユーザー層が完全に一致しているため、従来の採用媒体ではなかなかリーチできなかった若い世代にダイレクトに訴求することが可能になりました。
また、若い世代は長文を読むことを避ける傾向があり、文字情報だけでなく動画や視覚的に楽しめるコンテンツを好みます。そのため、短尺動画で視覚的にアピールできるTiktokは、若年層の注目を集める上で非常に効果的なプラットフォームとなっています。
2-2. 企業の認知度向上やブランディング効果が期待できる
Tiktokは単なる採用ツールという枠を超え、企業ブランディングや認知度の向上にも効果があります。面白さや共感を誘う動画が拡散されることで、求人活動をしながら同時に企業のブランドイメージも広く伝えることができます。
たとえば、社内イベントや社員の日常、ユニークな社風を伝える動画を継続的に投稿することで、求職者だけでなく一般ユーザーからも注目され、企業のイメージアップや好感度向上につながります。また、社員自らが出演して発信することで、リアルな企業文化が伝わり、結果として親近感や信頼感が高まるというメリットもあります。
2-3. 他のSNSにはない拡散性・話題性がある
Tiktokには独自のアルゴリズムがあり、「いいね」やコメントなどの反応が良い動画は自然におすすめ欄に表示され、ユーザー間でどんどん拡散されていきます。これはTwitterやInstagramなど他のSNSよりも強力な拡散力を持つ仕組みであり、企業が予想していた範囲を超えた多くのユーザーに届く可能性があります。
また、Tiktokのトレンドに乗った投稿やハッシュタグチャレンジを企業がうまく活用することで、一気に話題性が高まり注目を集めることも珍しくありません。このような拡散性と話題性を活かせば、短期間で多くの求職者にアプローチでき、応募数の増加や採用成功率の向上にも大きく貢献します。
3. Tiktok採用の具体的なやり方
Tiktok採用を導入したいと思っても、実際に何から始めればいいのか戸惑う方もいるでしょう。ここでは、Tiktok採用の始め方から運用、求職者への効果的なアプローチ方法までを具体的な手順に沿って解説していきます。
3-1. (1)採用専用アカウントを開設し運用体制を整える
Tiktok採用を始めるために必要なのは、企業としての採用専用アカウントを開設することです。通常の企業アカウントと採用アカウントは目的が異なるため、採用活動に特化したアカウントを作成し、求職者に必要な情報を効果的に発信できるようにすることが重要です。
まずは公式アカウントのプロフィール欄を整備しましょう。企業名や採用サイトへのリンク、簡潔な企業紹介文を記載します。特に採用サイトやエントリーフォームへの導線を明確にしておくことで、動画を見て興味を持ったユーザーがスムーズに次のアクションへ進めます。
また、運用担当者を決め、撮影から編集、投稿までの役割分担を明確にします。Tiktokは継続的な投稿が必要になるため、計画的に運用する体制を整えることが大切です。頻度や内容の方針を決定し、担当者が迷わずに運用できるように運用ガイドラインを策定しておくとスムーズです。
3-2. (2)ターゲットに響く動画コンテンツを企画・制作する
次に、採用ターゲットとなる若年層の関心を引きつける動画コンテンツを企画・制作します。Tiktokユーザーは「面白さ」や「親近感」、「共感性」を求める傾向があるため、それらを意識したコンテンツ作りがポイントです。
具体的な内容としては、社内の様子をリアルに伝える「職場紹介動画」、社員が日常的な業務を楽しげに紹介する「社員の日常動画」、先輩社員による仕事紹介や就活アドバイスを盛り込んだ「社員インタビュー動画」などが効果的です。また、若い世代が気になる給与や福利厚生、オフィスの設備などを動画内でユニークに紹介すると、より関心を引くことができます。
動画制作のポイントは、凝りすぎず自然体で投稿することです。社員自身が出演し、リアルな職場環境や人柄をアピールすることで求職者に親近感を与えることができます。
3-3. (3)広告配信やハッシュタグを使って投稿を拡散する
動画の企画や制作時には、「ターゲットとなる求職者が何を求めているか」を明確にする必要があります。若年層は職場の楽しさや仲の良さを特に重視する傾向があるため、社内イベントや社員同士のやり取りを中心に動画を作ると効果的です。
また、実際の社員にインタビューを行い、仕事内容のリアルな一面や魅力を語ってもらうのもおすすめです。求職者が実際に働くイメージを持ちやすくなり、興味を持つきっかけになります。動画は短い時間で端的にまとめ、冒頭の3秒で視聴者を引き込むように工夫しましょう。文字や効果音を使って飽きさせない演出を加えることも効果的です。
3-4. (4)興味を持ったユーザーを採用サイトへ誘導する
Tiktok投稿が話題になり多くのユーザーが関心を持ったとしても、そのユーザーを確実に応募までつなげるための仕組み作りが重要です。そのためには動画の投稿だけで終わらず、必ず採用活動につなげるための明確な導線を設計することが大切です。
具体的には、動画投稿の最後やプロフィール欄に採用サイトへのリンクを設置し、求人情報やエントリーフォームへ直接誘導します。また、採用専用のランディングページを用意し、動画を見て興味を持ったユーザーがすぐに応募行動を起こせるような仕組みを整えることがポイントです。
さらに、コメント欄を活用してユーザーの質問に丁寧に回答したり、DM機能を使った個別対応を行ったりすることで、求職者との距離が縮まり、採用への具体的なアクションにつながります。
4. Tiktok採用を成功させるためのポイント
Tiktokを活用した採用活動は、手軽に始められる一方、単純に動画を投稿するだけでは十分な成果は得られません。効果を最大限に引き出し、多くの求職者を獲得するためには、企業として押さえておくべきポイントがいくつかあります。
たとえば、以下のようなポイントを押さえることでTiktok採用を成功に導くことが可能です。
- 企業イメージに合った投稿内容を心掛ける
- 投稿頻度やタイミングを最適化する
- ユーザーとの積極的なコミュニケーションを行う
- 分析ツールを活用し効果測定・改善を繰り返す
ここからは、Tiktok採用を成功に導くための具体的なポイントについて詳しく解説していきます。
4-1. 企業イメージに合った投稿内容を心掛ける
Tiktok採用を成功させるために重要なのは、投稿する内容が自社のブランドイメージや求職者に与えたい印象にマッチしていることです。動画コンテンツは企業の「顔」となります。楽しさやユニークさを伝えることも大切ですが、あまりにも企業の実態とかけ離れた内容を投稿してしまうと、入社後のミスマッチが発生してしまう恐れがあります。
たとえば、明るくアットホームな雰囲気を訴求したい企業なら、社員同士の楽しげな日常風景やイベントの様子を中心に投稿するとよいでしょう。一方、プロフェッショナルさや誠実さを重視する企業であれば、社員インタビューや仕事風景を中心に投稿すると、求職者にリアルな企業イメージを与えることができます。
3秒~5秒ほどの冒頭で企業の特徴を簡潔に伝え、印象を残す工夫を心掛けることが重要です。
4-2. 投稿頻度やタイミングを最適化する
Tiktokは動画の投稿頻度やタイミングが非常に重要なSNSです。投稿頻度が低すぎるとユーザーの目に留まらず忘れられてしまいますが、逆に多すぎてもフォロワーが離れる原因になります。一般的には週に2〜3回程度の投稿を継続することが望ましいとされています。
また投稿時間帯も重要なポイントです。ターゲットとなる若年層は学校やアルバイト終わりの夕方から夜間にTiktokを活発に利用する傾向があります。そのため、夕方から夜の時間帯(18時~22時)を狙って投稿すると、視聴数やエンゲージメント率が高くなる傾向があります。
このように投稿頻度やタイミングをターゲット層のライフスタイルに合わせて最適化することで、採用効果を高めることができます。
4-3. ユーザーとの積極的なコミュニケーションを行う
Tiktok採用において、単に動画を投稿して待つだけでなく、ユーザーとの双方向のコミュニケーションを意識的に行うことがポイントです。コメントやDMなどで求職者やユーザーとの交流を深めることで、企業に対する親近感や信頼感を醸成できます。
具体的には、動画へのコメントに対して積極的に返信したり、質問コーナーを設けて求職者の疑問に動画内で回答したりする方法があります。採用担当者や社員自身が直接コミュニケーションを取ることで、求職者は企業の雰囲気をリアルに感じ取ることができ、応募への心理的ハードルも下がります。
また、ユーザーの反応をもとに次回の動画コンテンツを改善していくことで、より求職者の興味を惹くコンテンツ作りが可能になります。
4-4. 分析ツールを活用し効果測定・改善を繰り返す
Tiktok採用では、投稿後の効果測定や改善も欠かせません。Tiktokが提供している分析ツール「Tiktok Analytics」を利用すると、動画の再生数や視聴時間、エンゲージメント率などを詳細に把握できます。
これらの分析データを活用し、どのような投稿内容が求職者の興味を引いているか、どの時間帯が最も効果的であるかを定期的に振り返り、PDCAサイクルを回すことが重要です。効果測定に基づいた改善を繰り返すことで、企業の採用力や認知度を高めることができ、Tiktok採用の成功率を高めることが可能です。
まとめ
Tiktok採用は、Z世代を中心とした若年層へのアプローチに最適な新しい採用手法として注目されています。短尺動画の特性を活かし、職場のリアルな雰囲気や社員の個性を効果的に伝えることで、求職者の関心を引きやすくなります。
ただし、成果を出すためには企業イメージに合った投稿内容や最適な投稿頻度、ユーザーとの積極的なコミュニケーションなど、ポイントを押さえて運用することが重要です。さらに分析ツールを使った効果測定と継続的な改善を行えば、認知度向上や優秀な人材獲得につながるでしょう。